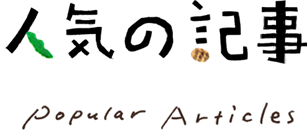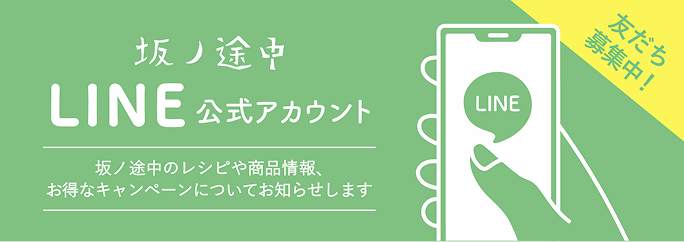2024年9月30日(月)に「サステイナブルファーマーズラボ(SFL)」第8回を開催しました。このイベントは、生産者さんの学びあいの場として、坂ノ途中が企画・運営しています。
今回はオンラインでの開催でした。参加者は約160名で、大部分は生産者の方でした。一方で、政府機関、関係企業、メディアの方々の参加もありました。
第8回の趣旨
第8回は、環境負荷の小さい農業のあり方について考えました。参加者の方々の多くは、有機農業に取り組んでいるかと思います。そして、その理由の一つは、有機農業の環境負荷が小さいためかもしれません。
ですが、有機農業と環境負荷の関係について、じっくり考える機会はなかなかないように思います。そういう機会になればと思い、第8回を企画しました。
講演内容
有機農業と環境負荷の関係を考えるために、土壌学者・藤井一至さん(森林総合研究所)に講演いただきました。講演タイトルは「明日はどっちだ? 土から考える日本の農業」でした。
藤井さんの講演は、農業を長い時間スケール(数億年)で見るものでした。そもそも「土とは何か」「農業とは何か」から考え始め、その中に有機農業を位置づけるものでした。
講演の要点を、私なりにまとめると、以下のようになります。
・土は、岩石、気候、生物の相互作用によって、気の遠くなるような時間をかけてできた。
・だから人間は、土を選ぶことはできず、作物や農法の選択によって適応するほかない。
・有機農業は、その適応の一つである。当然、場所や条件によって、有機農業が最適な選択肢でないこともあり得る。
討論内容
以上の講演をもとに、藤井さん、小野邦彦(坂ノ途中・代表)、小松光(坂ノ途中・主任研究員)で討論しました。
討論で私の印象に残ったのは、リジェネラティブ農業の話でした。藤井さんは、リジェネラティブ農業は、アメリカの文脈には合っているが、日本ではどうだろうか、とおっしゃっていました。
この発言の背景を、私は次のように理解しました。アメリカの土壌劣化の激しい地域では、土壌を復元する(リジェネレイト)のが唯一の選択肢かもしれない。さらに、「劣化した土壌を復元して生きる」という考え方は、「原罪により堕ちた人間が、再び救われる」というキリスト教的な物語と親和性が高い。しかし日本では、土壌劣化がさほど深刻ではなく、キリスト教的世界観も一般的ではない。
このお話から、「農業の理念を生きたものにするためには、現実の文脈とすり合わせていく努力が大事だ」ということを、私は学びました。
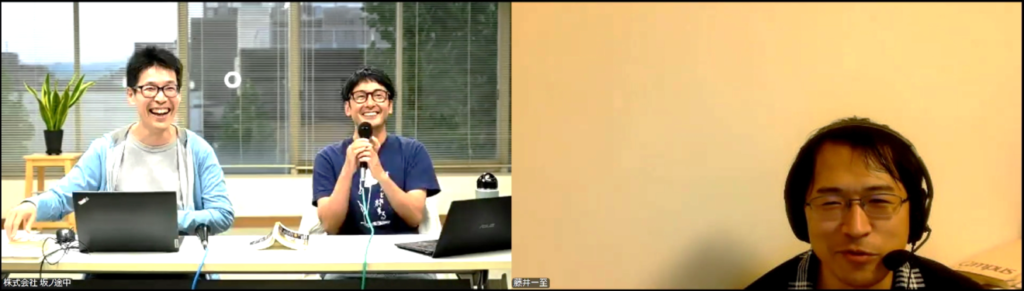
明日はどっちだ
今回のSFLで「明日の農業が見えた」という方は、あまりいないのではないかと想像します。ですが、藤井さんのお話で、「明日の農業は見えなくて当然だし、迷いながら自分なりにしっくりくることを探していけばよい」と感じ、勇気づけられた方がいらっしゃったようです。
実際、SFL終了後のアンケートでも、以下のようなコメントがありました(若干表現を変えています)。
・持続的農業へのアプローチが多岐にわたっているという話が興味深かった。
・すべてはバランスであり、自分と環境にあったものを見つけることが重要だと感じた。
私たち坂ノ途中も迷うことが多いですが、文脈をよく見ながら、明日の農業について考え続けていこうと思います。
小松 光(坂ノ途中の研究室)