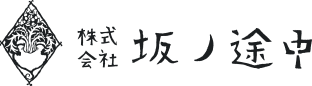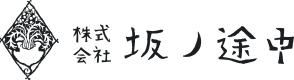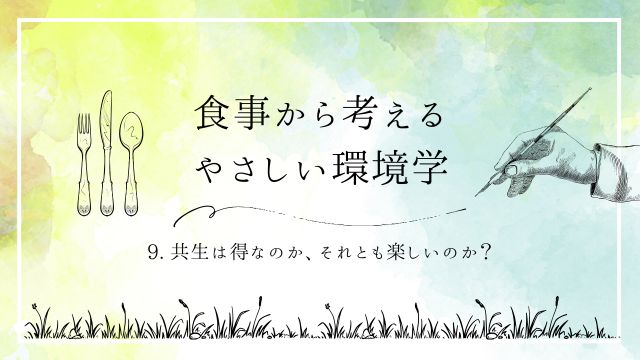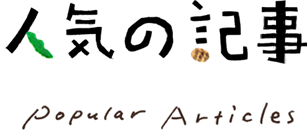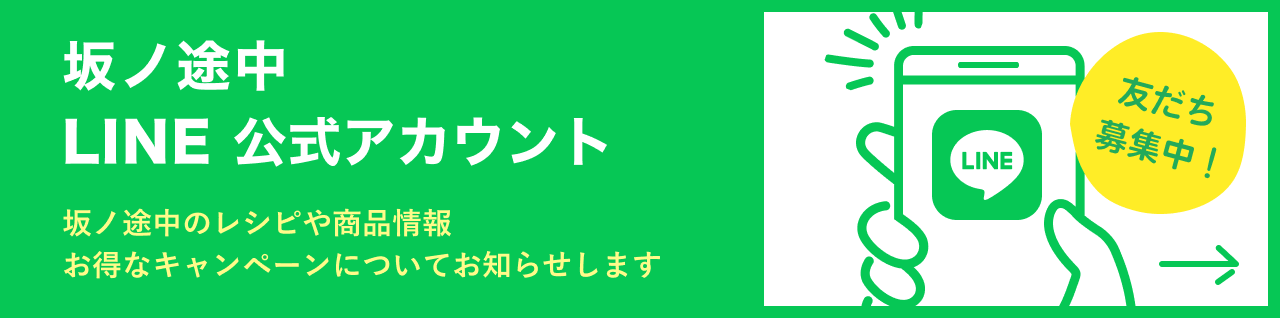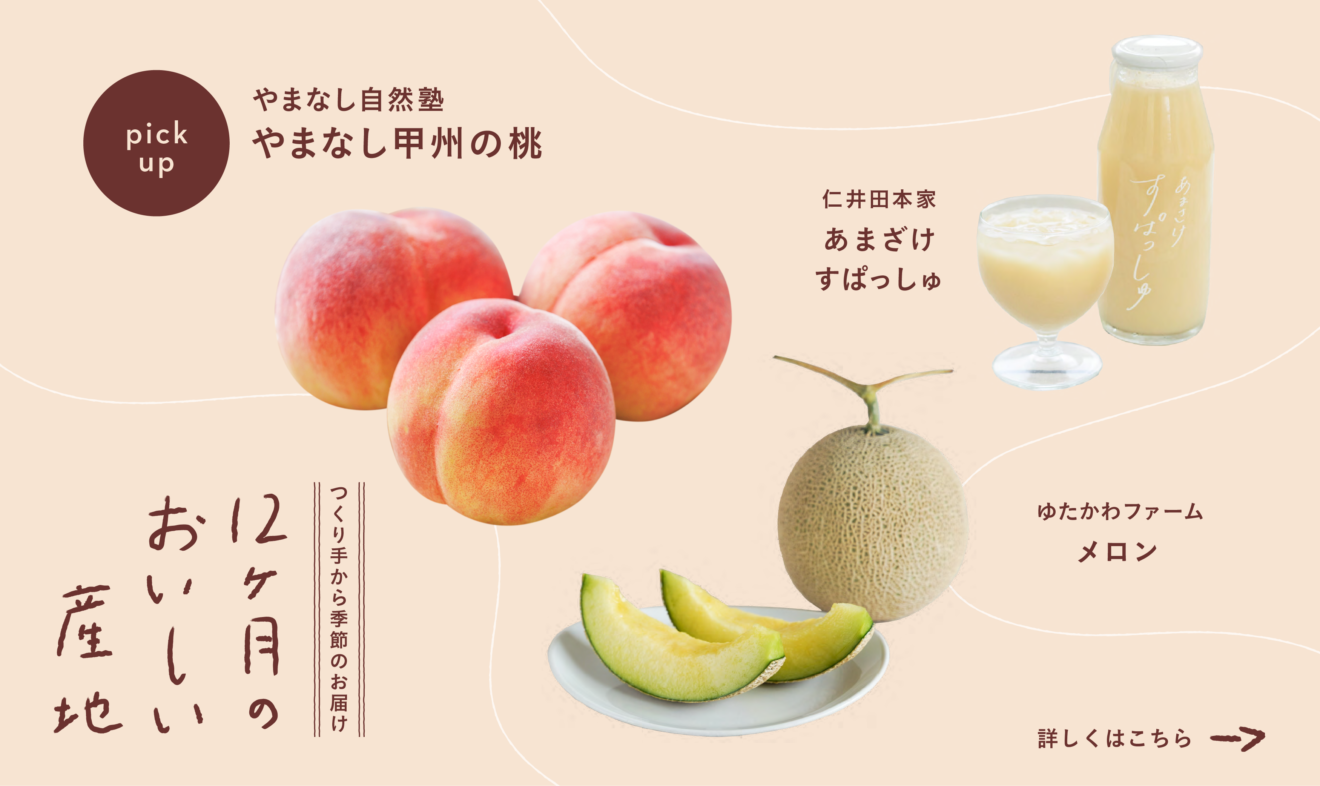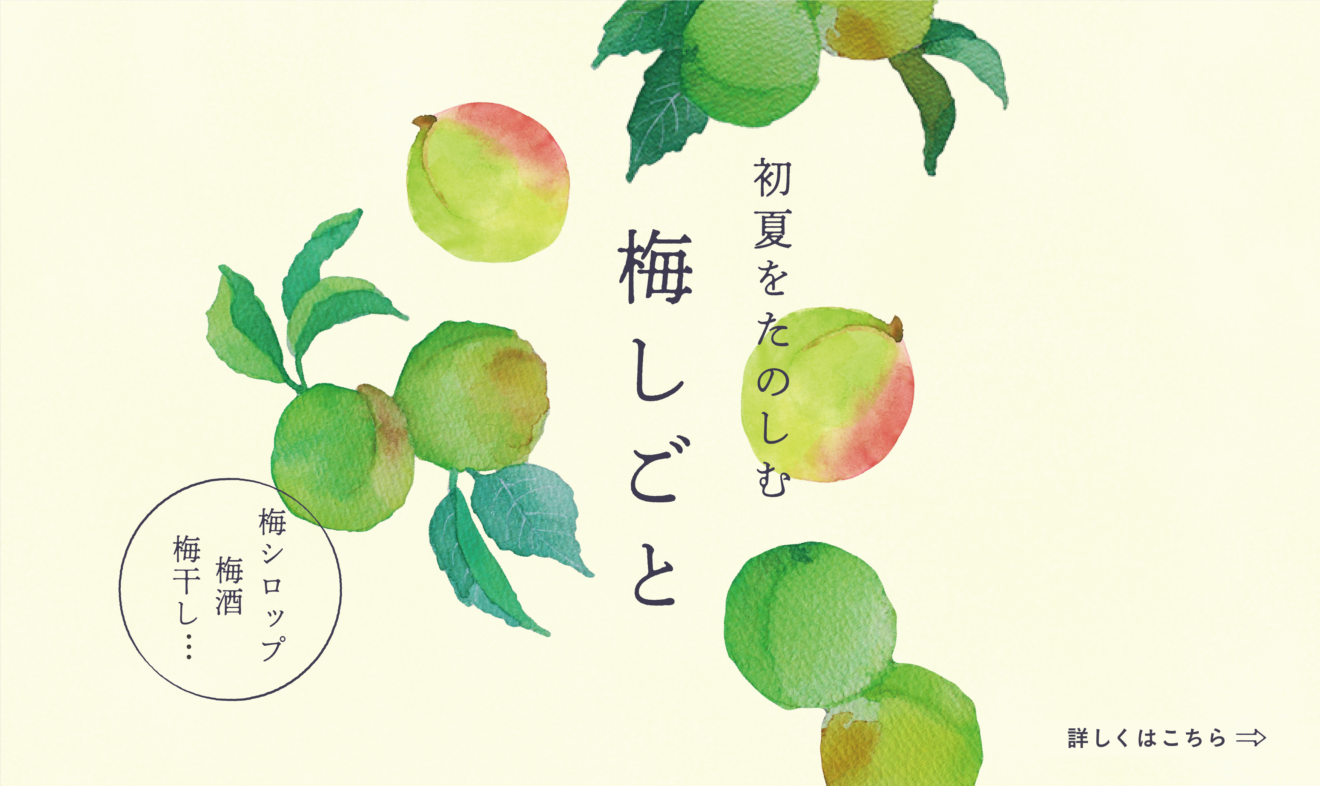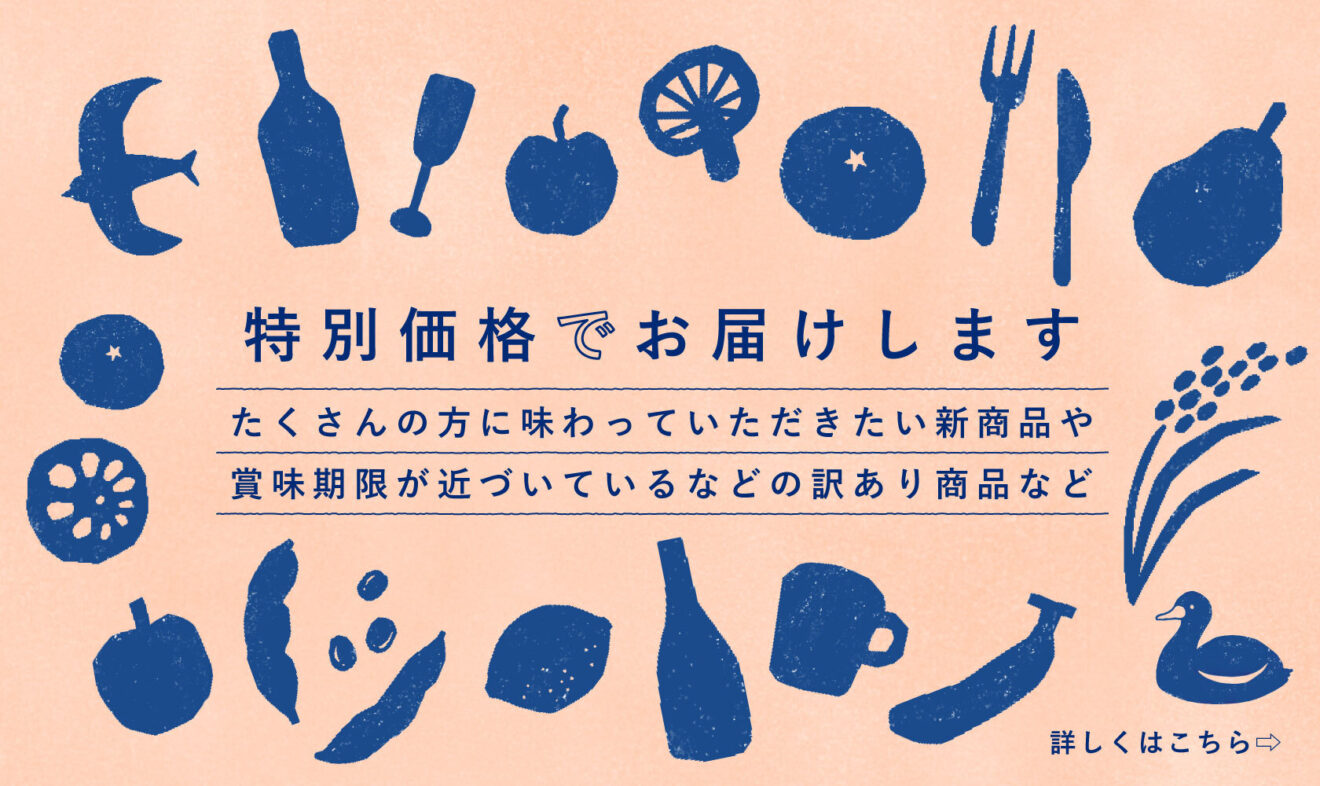みなさん、こんにちは。坂ノ途中・研究員の小松光です。
この連載では、もう長らく化学肥料や化学農薬、そして有機農業の話をしています。ちょっと飽きてきたかもしれませんが、今回でその話も終わります。あと少しお付き合いいただけたら、と思います。
9月の記事で、日本では、化学肥料や化学農薬の使用量を減らしていけるのでは、という話をしました。日本では食糧増産の必要があまりなく、むしろ心配なのは汚染や資源枯渇だからです。
ただ、9月の記事の書き方には少し引っ掛かるところがあります。というのも、記事は「化学肥料や化学農薬の使用量を減らすのが人間にとって得だ」という言い方をしているからです。
たしかに得だとは思うのですが、それがすべてでしょうか? というのも、先月見たように、私たちは、他の生き物と共生したいと思うようになってきています。これも「得」という観点から考えてよいものでしょうか?
他の生き物との共生は、「得」よりも「楽しい」という観点から考えた方がいいのではないか、と私は思っています。

まず他の生き物との共生が得かどうかは、実に難しい問題です。他の生き物との共生は得だ、という考え方は存在します。よくある考え方は、こんな感じです。生物種が多様な方が、生態系が安定するので、生態系からサービスを受けている人間に利益がある。この言い方はよく使われるのですが、私にはよくわからないところがあります。
たしかに、いろんな生物がいると生態系が安定する、というのは一般的に成立します。ですが、生物の種数が変化したときに、目立って生態系の安定性が変わるのは、おそらく種数が少ない場合です。日本のように生物種が多い場所では、種数が多少変化しても、生態系の安定性はあまり変化しないかもしれません。こう感じてしまうので、日本の現状を考えたとき、他の生き物との共生が本当に得とまで言えるか、私にはわかりません。
むしろ、「楽しい」という観点から考えてはどうだろう、というのが私からの提案です。他の生き物との共生が楽しいのは、生き物が好きな一部の人だけだろう、という反論もあるかと思います。ですが、生き物がさほど好きでもない人も、実は生き物の存在を無意識に楽しんでいるかもしれない、と私は最近思うようになりました。
というのも、最近、ある一群の研究を知ったからです。それらの研究は、生物の種数と主観的幸福度の関係を調べています。「主観的幸福度」とは、「収入の多寡」や「家族の有無」のような客観的なものではなく、「自分がどのくらい幸福と感じているか」という主観的なものです。これらの研究は、生物の種数が多い場所の住人のほうが、主観的幸福度が高い傾向にあることを報告しています。
生物といってもいろいろいますが、とくに鳥との関係を見出している研究が多くあります。そうした研究は、鳥の種数が多い地域で、主観的幸福度が高い傾向を報告しています。しかも、鳥の種数の主観的幸福度への影響は、かなり大きいようです。主観的幸福度には、収入も大きな影響を与えることが知られていますが、鳥の種数は収入と同程度の影響を与えているという報告もあります。
ここで大事なのは、上の研究が、とくに鳥好きの人だけを対象としたものではない点です。つまり、とくに鳥が好きでなくても、多くの人は無意識に鳥の声を聴いていて、影響を受けているのかもしれないのです。

このように考えると、「他の生き物と共生するのは楽しいのでは」と言うこともできそうです。もちろん、生物の種数と主観的幸福度の関係が、どのくらい一般的なものであるか、今後の研究が必要です。また、どんな生き物とも楽しく共生できるわけではないことも確かです。それでも、「楽しい」を起点にして、化学肥料や化学農薬の使用量を減らしていくのも、一つの方向ではないかと私は感じています。
みなさんが、化学肥料や化学農薬をあまり使わない農家さんを応援してくださったら、だんだんといろんな生き物が生きられる環境が整っていくかもしれません。そして、農家さんや地域の人、あるいは、そこを訪れた人たちが少し楽しい気持ちになるかもしれません。
こんな社会は素敵だなあ、と私は思います。人々や生き物の間に、ルーズな共同性がある社会。こういう共同性は、ふだんほとんど意識しないのだけれど、それによってみんなが少しだけ楽しい気持ちになっている。そんな社会がありえるような気がしています。
この数回、実に複雑なお話を続けてきました。それでも、多くの方が記事を読み続けてくださっているのを感じています。ありがとうございます。とても勇気づけられます。
次回は、少し肩の力を抜いて読める話にしようかと思っています。それでは、また。
![]() 小松 光(坂ノ途中の研究室)
小松 光(坂ノ途中の研究室)