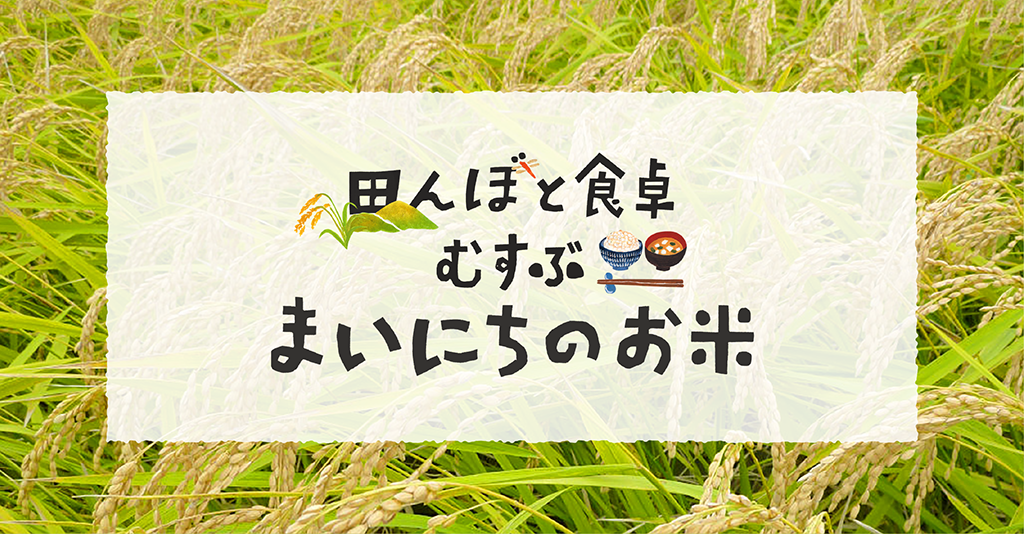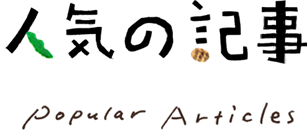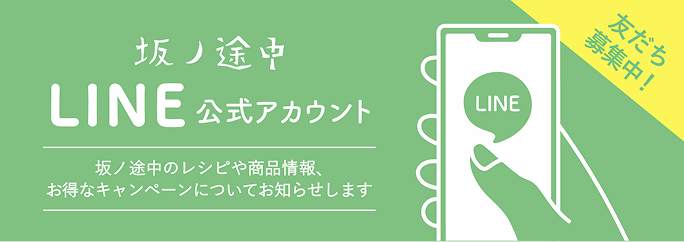気候や土壌と向き合い、環境に配慮して育てられたお米の定期宅配「田んぼと食卓むすぶお米」。
それぞれのお米の産地の景色やつくり手の想い、味わいをご紹介します。
●
地域の農業をつなぐ

北海道の道央、札幌市や新千歳空港から車でおよそ1時間ほどの距離に位置する、栗山町。その街並みからすこし離れた、なだらかな丘陵地帯の裾野に、杵臼(きなうす)という地区があります。
「麦畑の広がる田園の向こうに、街並みが見えるんです。ここの、好きな景色ですね」
お話を伺ったのは、杵臼の農家に生まれ、二十歳からこれまで四十年農業一筋という、きなうすファームの篠田勝さん。美しい風景、地域の農業を守っていきたいという想いから、2007年、農業生産法人のきなうすファームを、地域の2軒の農家とともに立ち上げました。

きなうすファーム・篠田さん
「食卓とつなぐ、杵臼をつなぐ」という言葉には、この地で育った作物を自分たちの手で届け、食卓に近いところで関わっていけたら、という願いが込められています。
食べる人に農業の現場を理解してもらうことも、農業を守ることにつながる。そんな想いから、農園では、田植えや稲刈りの農業体験の受け入れも積極的に行っています。田んぼでは、子どもも大人もいっしょになって、気持ちのいい汗を流します。

北海道の気候とともに、みずみずしいお米を

本州にくらべて、冷涼な気候の北海道。お米の栽培においては、虫や病気の発生が比較的少ないといわれています。きなうすファームでは、この気候を活かしながら、極力農薬の使用を抑えたお米づくりをしています。
種もみの消毒には、農薬を使わずお湯で消毒する方法(温湯消毒)を取り入れ、すこやかで元気な苗を育てます。また、田んぼの地層に切り込みを入れて排水性をよくすることで、稲の生長を手助けしたり、秋に稲わらを鋤き込んで、春にはまた稲が有機質として吸収できるような土づくりをしたり。
お米の乾燥も丁寧に行います。一気に乾かすのではなく、ある程度まで水分量を減らしたら、乾燥機から出し、ひと月ほど休ませます。お米の状態を落ち着かせてからふたたび乾燥させ、もみすり。ゆっくりと時間をかけることで、ほどよく水分が保たれ、みずみずしい味わいを持続させることができるのです。
もみすり後は色彩選別機を導入することで、カメムシの食害により黒点がついてしまった米粒を取り除けるようにし、そのぶん、カメムシを防除するための農薬の使用は抑えています。
近年は、北海道でも夏の気温が上昇傾向にあり、高温障害や虫害も以前とくらべて多くなっているといいます。篠田さんも、ここ十年で気候ががらっと変わったことを実感されているそう。それでも、種蒔きや田植えの時期をずらしたり、水田に冷たい水を流し入れたりと、気候に応じた工夫をしながら、お米づくりを続けています。

食感しっかり、やさしい甘さの「ななつぼし」
「星空がすっごくきれいですよ。まわりに灯りがなにもないので」とほほ笑む篠田さん。
澄みわたる空気のなか、杵臼の田んぼの夜空には、北斗七星がきれいに瞬きます。
そんな星空のように、きらきらと輝くお米をイメージして名付けられた「ななつぼし」は、北海道を代表するお米の品種の一つ。篠田さんが日々食べているのも、このななつぼしだそうです。もちもち、ほどよい粘り気がありながらも、食感がしっかりとしていて、あっさりとした食べ心地。毎日食べていても飽きのこない、バランスのとれた味です。
篠田さんのおすすめは、塩むすび。お米の味わいが一番よくわかるからだそう。みずみずしい甘み、お米らしい香り。ひとくちずつ、味わってみてくださいね。

| きなうすファームのななつぼし ・産地 北海道栗山町 ・栽培基準 特別栽培農産物相当(化学合成農薬の成分使用回数、化学肥料由来の窒素成分量が栽培地域で慣行的に使用されている量の半分以下) 坂ノ途中の特別栽培についての考え方はこちら |
●
季節とともに移りゆく色。
水や土、草花と生きもの。
にぎやかな田んぼの景色を一緒に育んでいきませんか。
おいしいお米を味わうことが田んぼとわたしたちの食卓をむすび、未来につづく農業や暮らしを考えるきっかけとなりますように。