vol.15
人は目に見えるものだけを世界と感じてしまいがちです。自分も子どものころは学校と家が世界のすべてで、テレビに映っているものはなにもかもがフィクションであるかのように感じていましたが、本との出会いによって視野が大きく広げられました。
高校の図書館でたまたま手に取ったレイチェル・カーソンの「沈黙の春」。テレビで見た環境問題のドキュメンタリーよりもはるかにインパクトの大きなものでした。そしてこの本がきっかけとなって多くの本を読み、さまざまの視点から紐解かれた歴史や物事を知ることとなり、未来を想像するきっかけを掴むことができました。
私たち日本人の多くは、当たり前のように毎日食事をしています。米、肉、野菜。スーパーマーケットに行けば多くの食材が並んでいます。しかし歴史を振り返ると、食べ物に恵まれていた時代や地域は限られたものでしかないことがわかります。現代社会は恵まれた「食」を享受しているといえますが、それは非常に不安定なしくみの上で成り立っていることも。
「食」の過去とそして未来を考えるきっかけになった本をご紹介したいと思います。
文明を左右する土
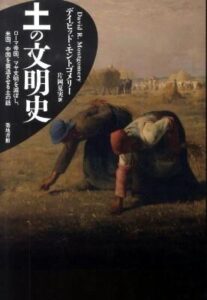
|
「土の文明史 ローマ帝国、マヤ文明を滅ぼし、米国、中国を衰退させる土の話」 |
1冊目は土のこと。私たちの食卓を支えているのは足下の土です。野菜や、植物を食餌とする家畜(肉)は土がなければ存在できないでしょう。
本書では、1万年前から現在までの世界中のさまざまな文明と土とのかかわりが取り上げられています。衝撃を受けるのは、文明の終焉の裏に土壌の荒廃が大きな影響を及ぼしていたこと。メソポタミアで都市文明を生みだしたシュメール人は、肥沃な大地に国家を建設したものの、過剰な灌漑よって土壌に塩分が溜まることを見抜けず、食物の収穫量の大きな減少を招いて、文明は没落への道筋を辿ったという話や、強大なローマ帝国の崩壊の一因となったのは土壌の流出による食物の生産性の悪化ではないかということも述べられています。
これらは、単なる過去の物語ではなく、いまなお土の問題を解決できない現代にそのまま当てはまる話です。
文明という時間軸にくらべて、土が生成されるには遙かに長い時間が必要です。古き文明をなぞるかのように、その土壌を収奪している現代の農業は、科学肥料を駆使したり森林を伐採して開拓することで問題を先送りにしていますが、これから先はどうなっていくのでしょうか。
土そのものについてコンパクトに知識を得るには藤井一至さんの「大地の5億年」もおすすめです。
人はいかに植物と戦い、利用してきたか

| 「たたかう植物──仁義なき生存戦略」 稲垣栄洋 筑摩書房 2015年 |
植物は動くこともできず、動物に一方的に食べられる側の生きもののように思います。そんな植物がどのように生き延びてきたのか。本書では「植物vs植物」を皮切りに「植物vs環境」「植物vs病原菌」「植物vs昆虫」「植物vs動物」そして「植物vs人間」までの話が描かれています。
植物のサバイバルゲームのなかでも、人間との戦いは独特です。田畑の実りは、自然の恵みのように受け止められがちですが、ほとんどの作物(植物)は人間が数千年という時間をかけて選抜、交配を繰り返してきたものです。私たちが食べている植物の多くは人工のものだということがわかります。
たとえば小麦。原種のヒトツブコムギは種子を弾き飛ばして子孫を増やすのですが、突然変異によって種子を飛ばせない株があらわれ、それを都合が良いとして人間が栽培をはじめ、今の小麦の姿になったと言われています。ほかにも、人間はさまざまな工夫や改造を植物にほどこしました。ダイコンは異常なほどに肥大をするようになったし、キャベツは葉を広げることもなく丸くなっています──私たちが目にする野菜のかたちです──。
こうして見ていくと、人間は植物に自在に手を加え、利用しているように思いますが、視点を植物の側に移すと、植物が人間を利用して形を変えさせたという見方もできるという指摘も興味深いものです。
地球でもっともバイオマス(生物体量)の大きな生物はサトウキビやトウモロコシです。宇宙人が地球を眺めると、これらの植物が地球の主で、人間はそれに奉仕しているように見えるかもしれません。
農業者の視点に学ぶ

| 「いま、米について」 山下惣一 講談社 1987年 |
長崎県唐津市の農業者で小説家の山下惣一さんの著作のひとつ。日本の経済成長や農政に翻弄される農村や農業者の姿を、その当事者として描いた迫力ある一冊です。
1986年からはじまったバブル景気の真っ只中で、産業界から農業の生産性の低さや補助金について批判を受けたことなどについて書かれたもので、時代を感じるところはあるのですが、行政、市場(マーケット)、農業者、それぞれの抱える問題についての深い洞察はいまでも説得力を持っていることに驚きます。
日本の社会のうねりに翻弄されてきた農業者の姿を、大局的に振り返りながら、ひとりの農業者の過酷な生活の実態が記され、まさしく血の滲む思いを感じさせられました。
マーケットからは生産性の改善が求められ、効率化をすすめると生産量が増えて価格が下がってしまうというジレンマ。補助金は農家を補助するためのものではなく、嫌なことをやらせるためのもの、つまり補助する側のためのもの。ハッとさせられる記述も多く、自分が農業のことを少しはわかっていたつもりでいたことに反省を促されました。
滅びてゆくローカルすし、その豊かさ

| 「だれも語らなかったすしの世界 わが国におけるすしの文化誌史的研究」 日比野光敏 旭屋出版 2016年 |
今の日本で「すし」というと、握りずし、ちらしずし、手巻きずしなどを思い浮かべる人が多いと思いますが、すしという食べ物はもっと幅広く、深い奥行きをもつもので、それぞれの風土によって、時代によって、季節によって、また風習によって、さまざまなバリエーションがあります。
食べたら消えてしまううえに、同じ人がつくっても時期や季節によって変化が生まれてしまう、再現性の極端に低い食べ物を研究している人たちの記録が本書です。
たとえばフナずしのような発酵ずしにも、各地にバリエーションがあり、地域ごとに、そして家ごとに作り方が違うことなど、ページをめくるたびにさまざまなすしとその歴史を楽しみながら知ることができます。
しかし、多くのすしの伝統が失われつつあることにも気づかされます。小魚をとっていた池が埋め立てられたり、外来魚が増えたことで小魚がいなくなったり、少子高齢化で技術が失われたりといった記述がちらほらと目立つのです。社会の発展の影で文化の多様性が失われるのはしかたがないところもありますがさびしいものです。
ローカルすしを気軽に試してみたいという方向けには岡田大介さんの「身近な食材で豪華に見せる 季節のおうち寿司」もおすすめです。
日本人の知らない肉のこと
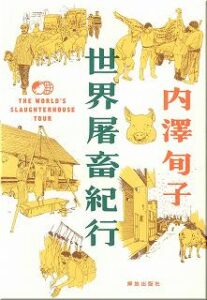
| 「世界屠畜紀行」 内澤旬子 解放出版社 2007年 |
本書は韓国、エジプト、バリ島、インド、チェコ、沖縄、東京、アメリカと世界各地の屠畜場を訪れ、屠畜とはいったいどういう行為であるのかを考えた記録です。
今、ほとんどの日本人はスーパーで清潔にパッケージされた肉しか目にする機会がありませんが、人が肉を食べるという原初的な風景はもっと多様で、恐ろしくもありどこか魅力的に映ります。
屠畜を残酷だと思う人がいるのはなぜか、日本ではなぜ屠畜に従事する人が差別されるのか、そういったことを屠畜場や食卓でのインタビューをもとに著者が発見していく様子を追体験できます。
イスラム圏では、肉屋は稼ぎが良いから羨望の職業とされていること、モンゴルの遊牧民たちが命を共有するかのような距離感で羊と接し、屠畜して食料とする文化、社会主義時代のチェコスロバキアでは肉屋が権力者に良い肉を流して稼いでいたという話。いまの日本では想像しづらいことも多く、いろいろな文化に触れて世界を旅する著者に、自分はどこか憧れを感じました。
工業化された食肉の生産や流通については「イーティング・アニマル」ジョナサン・サフラン=フォアが深堀りしており、憂鬱な気持ちになれます。また、畜産ではなく漁業については「聞き書き ニッポンの漁師」(2009, 塩野米松)がさまざまな漁師の何十年もの経験と考えを紹介しています。
日本にひろがる移民者の食
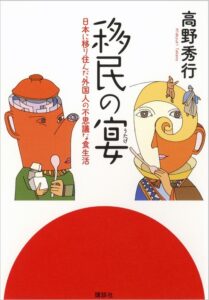
| 「移民の宴 日本に移り住んだ外国人の不思議な食生活」 高野秀行 講談社 2012年 |
日本に暮らす移民(1年以上の滞在をしている人)はおよそ250万人。その人たちが日本という国でどんな暮らしをしているのか、自分はほとんど知りませんでした。
高野秀行さんの「移民の宴」は、「食」を切り口としてさまざまな移民の人たちの日常の暮らしを眺め、描いています。
千葉県・成田のタイ寺院に集う人々、祖国の味のお弁当を楽しむ中華学校の生徒たち、群馬県・館林のロヒンギャのコミュニティ、被災した南三陸のフィリピン人たち、神奈川県・鶴見のブラジル人街。いろいろな場所でいろいろなかたちで、苦労しつつ自分たちの食文化をつないでいます。
強く印象に残ったのは、千葉県・西葛西のインド人コミュニティの話。高野さんは、コミュニティの長のチャンドラニさんとの会話から、「寛容」というのは、間違った行為を多めに見るということなら、それは上から目線ではないかと発見したパートです。
望ましいのは、排他的でないということかもしれません。日本は日本人だけが暮らしているわけではありません。目に見えるものだけが世界ではなく、身近にあっても見えていないものがたくさんあることに気づかせてくれるおすすめの本です。
著者の高野さんは、滅多に日本人が訪れることがないようなところを旅しては、その地にどっぷりと浸かった滞在記を多く著わしていて、ご自身では辺境冒険家を名乗っています。日本固有の食べ物と思われがちな納豆が、東南アジアの山岳地帯や韓国にも広がっていて、地域にまたがる食文化を形成していることを発見する「謎のアジア納豆──そして帰ってきた日本納豆──」もおすすめです。
日本人とプランテーションでの搾取

| 「バナナと日本人──フィリピン農園と食卓のあいだ──」 鶴見良行 岩波書店 1982年 |
バナナはスーパーマーケットに1年中並んでいるし、昔はバナナのたたき売りという露天売り(いわゆる啖呵売のひとつ)があったことを知ってはいても、日本人が20世紀の初頭からフィリピンのミンダナオ島に入植し、現地の人たちや欧米の企業と競うようにバナナ農園を拡大させてきた歴史はあまり知られていないと思います。
本書ではその過程や、第二次世界大戦を挟んで欧米の大企業がフィリピンの政財界と結託して住民を支配し、過酷な環境で酷使して搾取を繰り返してきたことを明らかにしています。
安価なバナナを享受している自分は、これらのことを知りませんでした。
プランテーションというと、世界史の教科書に出てくる、過去の外国での出来事だとばかり思っていましたが、現代の消費者である自分も無関係ではないのです。法を悪用して結ばれるアンフェアな契約、グローバル市場での競争。規制やボイコットという方法では解決することが難しい問題だと思いますが、まずは私たちもその構造に組み込まれていることを知るところが第一歩かもしれません。プランテーションという形態の農業は、多くの地域、多くの作物で問題となっていますが、まずは私たちに馴染みのあるバナナを取り上げた本書を選んでみました。
ほかにプランテーションの搾取については「トマト缶の黒い真実」からも、普段に食べているものの向こう側を知ることができます。暗澹たる気持ちになりますが。
人々は効率化を求め、食のリスクは高まる

| 「世界からバナナがなくなる前に 食糧危機に立ち向かう科学者たち」 ロブ・ダン 青土社 2017年 |
もうひとつ、バナナを冠した本を紹介します。
本書では、バナナ、カカオ、キャッサバ、小麦、ジャガイモなどの生産を脅かした病虫害の危機、その防御のために奮闘する科学者の姿が紹介されています。
20世紀の初頭に覇権を握った中米のバナナ産業が、疫病によってあっという間に壊滅してしまったこと、1845年から3年間に渡って引き起こされたアイルランドのジャガイモ飢饉は疫病が原因だったこと、アメリカの自動車会社のフォードが1920年代に巨額の資本を投下して運営したアマゾンの天然ゴムプランテーションが疫病の蔓延などで失敗におわったこと、アフリカで主食のひとつといわれるキャッサバに虫害が広がり、天敵となる寄生バチを持ち込んだこと、そのようなエピソードが科学者の姿とともに語られます。
どれも興味深い物語である一方で、すべての話の背景となっている市場(マーケット)のダイナミズムには憂鬱な気分を感じさせられます。
市場は、その顧客と供給者の求めるところによって、より生産性が高く美味しいものの普及が進んでいます。均一な種をもちいた大量生産。そのようなかたちでスケールメリットが得られると、商品は安価となり消費者は好んでその商品を選ぶようになり、市場はその商品によって席巻されます。農作物も家電も同じです。
安価なものを得られる消費者、パッケージ化した生産でコストを下げられる供給者、どちらにとっても良いことばかりのようですが、そこには破滅的なリスクが隠されています。そしてリスクの存在を理解していても、数十年に一度発生するかどうかというレベルでは、短期的な利益を追い求める民間企業は予防対策をとることは少なく、公的機関も予算を割くことはなかなかできません。
本書では、現実に世界が危機に瀕し、かろうじて残っていたマイナーな品種が疫病に抵抗性を持っていたり、害虫に対する天敵がいることを研究者が発見したことで、飢饉や災害を食い止めた事例も取り上げられています。
そう、生物多様性があることが人類の食を救うかもしれないのです。米やトウモロコシ、小麦など、単一の品種、作物を大規模に栽培していく農業、いわゆるモノカルチャーがすすむなかで農作物にパンデミックが起こる可能性は日に日に高まっています。地域の固有種や生態系に配慮した農作物を選ぶといった、生物多様性を意識した消費行動が将来の消費行動が将来の役に立つのかもしれません。
人類と食のきってもきれない歴史
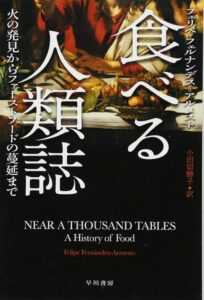
| 「食べる人類誌 火の発見からファーストフードの蔓延まで」 フェルナンデス=アルメスト・フェリペ 早川書房 2003年 |
人の食の歴史のなかには、パラダイムシフトのような変化をもたらした発見や発明がいくつかあります。本書ではこれを、火の発見による調理、医学へとつながる儀式化、畜産・農業・身分の分化、そして貿易やファストフードなどの産業化などとして著わしています。それぞれの出来事がどういう道筋を辿ったか、世界中の事例や研究成果をもとに論述されていて、文明の歴史は食の歴史に支えられ、大きな影響を受けていることがわかります。
ここに記されているのは「現在」までの話ですが、もしも新たな一章「未来」が付け加えるとすればどのようなものになるでしょう。2050年には地球の人口は100億人に達するという予測もあるなか、気候変動、土壌の喪失、プランテーションでの労働者の搾取、病虫害リスクの高まりなど、食を作り上げているメカニズムにはいくつもの不安な要素があります。これを克服していく食の生産方法を人類が見つけ出せることを祈ってはいますが、それはどう達成されるのか。食の未来を考えるためにもう一冊、取り上げます。
食の未来を考える

| 「みんなでつくる「いただきます」 食から創る持続可能な社会」 田村典江,クリストフ・D・D・ルプレヒト,スティーブン・R・マックグリービー 昭和堂 2021年 |
ここには、フードシステムの抱える問題を見つめ、未来の食のかたちをどうつくっていくべきかが書かれています。世界の研究者のアイデアや、世界各地の試行錯誤の事例など、自分にとって参考になることや考えるきっかけとなったことがたくさんありました。ただ、私たちの抱える食の問題はあまりに大きく、小さな改善の積み重ねでは解決ができない、社会の抜本的な改革が必要、ただその方法はまだ明らかではないともされています。
本書では、食品廃棄、生産者の減少と耕作放棄地の増加、世界に広がる飢餓など、今のフードシステムの問題点は露呈しているにもかかわらず、私たちはそれを受容していると指摘し、これを「人々が想像力の檻に囚われている」からではないかと問いかけています。自分は、新たなフードシステムを発見し、構築することが21世紀の人類の大きなミッションであると受け止めました。そこには大きく2つの選択肢があると思います。ひとつは今のフードシステムを動かしている経済のシステムを変えていくこと。もうひとつは現在の経済のしくみのなかで改善を図っていくこと。
経済システムを変革することは自分の想像力を超えた話になってしまいますが、坂ノ途中は今の経済・社会のしくみのなかで、環境負荷の小さな農業を広げるために、これに取り組む農業者の人たちの課題を解決しようとしています。お客さまや生産者の方たちの声に触れていると、みなさんがよりよい食のかたちをつくろうとしていることもわかります。行動の、声のひとつひとつは小さくとも、未来のために「想像力の檻」を壊す、その可能性があることを感じています。
●片山大











