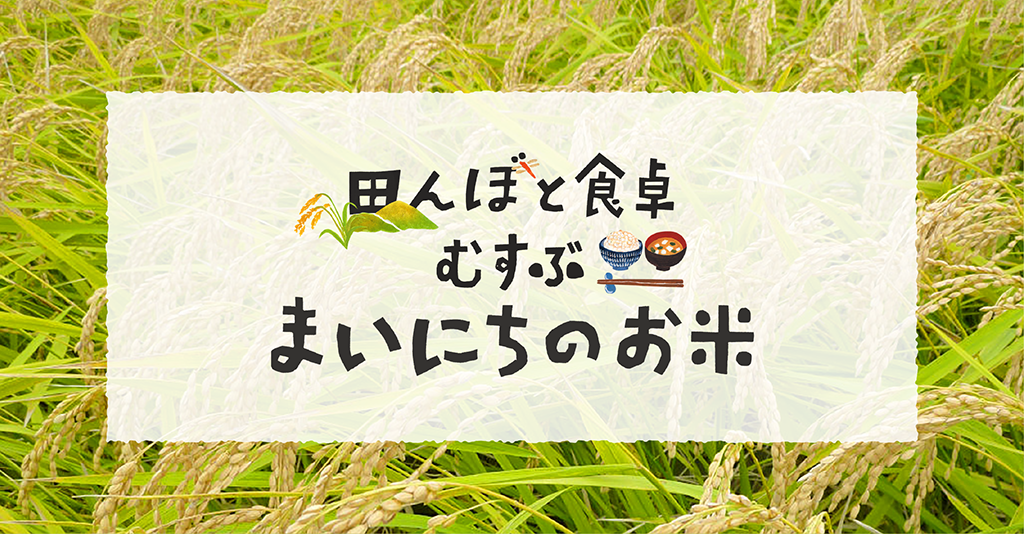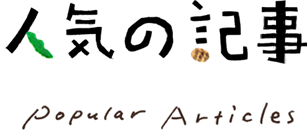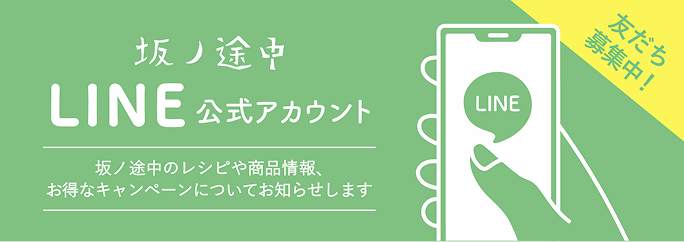気候や土壌と向き合い、環境に配慮して育てられたお米の定期宅配「田んぼと食卓むすぶお米」。
それぞれのお米の産地の景色やつくり手の想い、味わいをご紹介します。
●
水の豊かな、石清水八幡宮の歴史あるまちで
京都府南部の八幡市は、国宝・石清水八幡宮の門前町として歴史のある地。木津川、宇治川、桂川の三つの河川が合流する地点に位置し、かつては八幡五水と呼ばれる清らかな湧き水で知られていたように、水に恵まれた場所です。
この地で代々つづく、京都辻農園の辻典彦さんが「京都八幡の石清水」の生産者。お米のほかに竹林では筍を栽培し、春には白子筍を出荷してくださっています。
「できるだけ自然に近い環境で、本当においしいものを作りたい」 その想いから、妥協することなく、試行錯誤を積み重ねている辻さん。情熱と創意工夫の、一部をご紹介させてください。
苗にとって心地よい環境を

辻さんの田んぼでは、稲と稲のあいだに大きな隙間が空いています。一見ふしぎな植え方ですが、秋になると一面たわわに稲穂が実ります。隙間が、苗にとって心地よい環境をつくっているのです。
一つは、風通しの良さ。いつも新鮮な空気が田んぼ全体に行き渡ることで、病気にかかりにくく、健康なお米が育ちます。
また、日当たりも良好です。水を張った水田は鏡のようになり、上からも下からも苗にたっぷりと日光を浴びせることができます。
そして、田んぼの隙間には水鳥が舞い降ります。鳥たちが泳ぎながら足で泥をかき混ぜることで、雑草も生えにくくなります。
生きものたちとの共存

水鳥だけでなく、タニシや虫など小さな生きものとの共存も図っています。辻さんは年月をかけてその関係を築いてきました。
たとえば、大きなタニシは、はじめは厄介者でした。田植え直後のやわらかい苗を食べ尽くされていたからです。どうしようもなく、しぶしぶ殺虫剤を撒いた年、その田んぼには今までなかった雑草が生い茂りました。タニシは、雑草も食べてくれていたのです。
辻さんは、タニシと共存できる方法を考えはじめました。気づいたのは、どうやらタニシはやわらかい草が好きらしいということ。そこで、苗を太く、固く、強く育てるために、重いローラーで田植え前の苗を何度も踏みつけ、厳しく育てることを試みました。すると、タニシは苗を食べることなく、まわりの雑草だけを食べるように。
以来、除草剤や殺虫剤などの農薬に頼ることもなくなりました。田んぼにはタニシや虫が増え、それを餌にする鳥たちも多く集まるようになり、よい循環が生まれています。
時間をかけて、うまみを引き出す

お米のおいしさは、育て方だけでなく、収穫後の乾燥の仕方にも大きく左右されます。辻農園では、低温でゆっくりと乾燥させることを心がけ、お米の味わいを追及しています。
秋になると、ちょうど良い刈り頃である「刈り旬」がきた田んぼから順に収穫。気温の低い夕刻に乾燥をはじめ、夜間、翌日の昼間、そしてさらに夜間の36時間以上(通常の4~6倍の時間)をかけて低温で乾燥させます。じっくり時間をかけることで、お米の風味や香り、甘みが均一に引き出されるのです。

こうして、本物のおいしさを求め、愛情たっぷりに育てられた辻さんのお米「京都八幡の石清水」。うまみと甘みのバランスがよく、上品で香り豊かな味わいです。山椒じゃこ、山椒昆布など繊細な香りのご飯のおともと、相性ぴったり。ふっくらと炊いて、召し上がってみてくださいね。
|
京都八幡の石清水 |
●
季節とともに移りゆく色。
水や土、草花と生きもの。
にぎやかな田んぼの景色を一緒に育んでいきませんか。
おいしいお米を味わうことが田んぼとわたしたちの食卓をむすび、未来につづく農業や暮らしを考えるきっかけとなりますように。