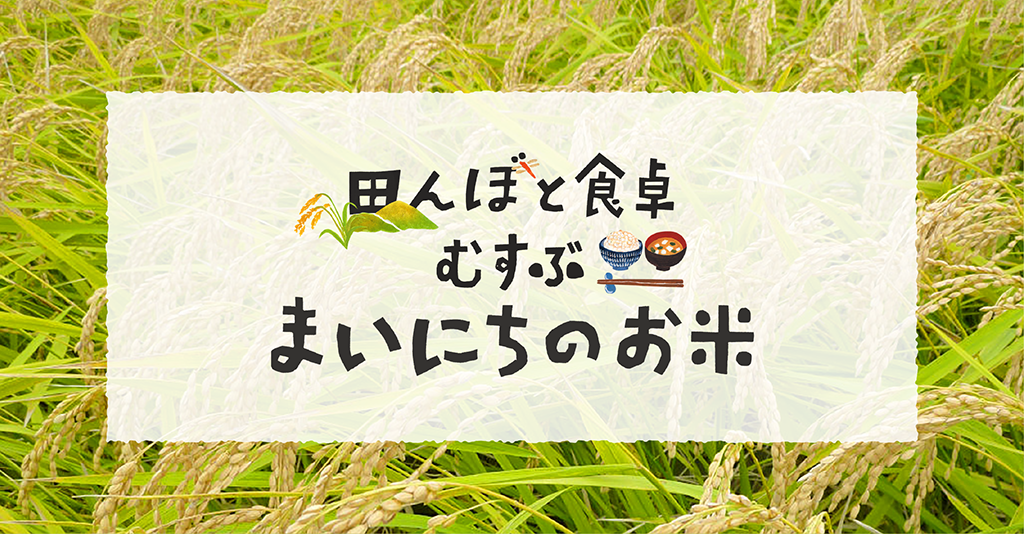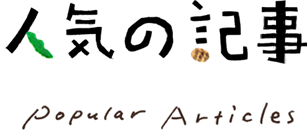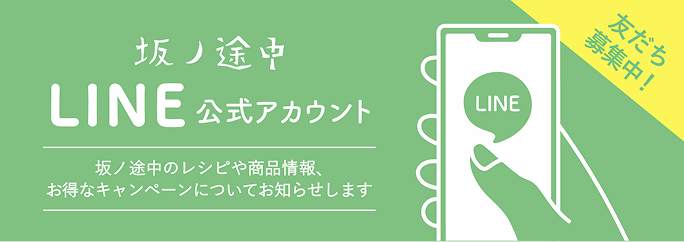気候や土壌と向き合い、環境に配慮して育てられたお米の定期宅配「田んぼと食卓むすぶお米」。
それぞれのお米の産地の景色やつくり手の想い、味わいをご紹介します。
●
晴れの国、岡山。倉敷でのお米づくり

JR山陽本線、岡山駅と倉敷駅のちょうど中間あたり、岡山県倉敷市の下庄という地域に、山﨑農園の田んぼはあります。
「いまではこの辺りも住宅が多くなったけれど、昔は一面に田んぼが広がっていて、麦やイ草の栽培も盛んに行われていたんですよ」と、子どもの頃を振り返るのは、山﨑農園の園主、山﨑正人さん。この土地で生まれ育ち、さまざまな作物で彩られる景色を見守ってきました。
温暖な気候の岡山県南部では、麦やイ草と、お米の二毛作が行われてきました。イ草は、倉敷の繊維産業の一つの畳表や、民藝の文化を支えた作物ですが、いまではつくり手が減り、その土壌を活かして、お米の栽培が行われています。
山﨑さんが育てているのは、日本に明治時代から伝わる在来種のお米である京都の「旭」を、晴れの国岡山に持ち帰り選別した「朝日」。昔ながらのあっさりとした味わいのお米で、肥料を多く与えずとも、太陽をしっかりと浴びてぐんぐん育つ、地力(じりき)のたくましさがあります。
よく考える、常に考える、深く考える

農家になる前は、自動車部品メーカーで設計の仕事を担当していたという山﨑さん。ものづくりのよろこびはあったものの、お客さんからの評価を直接うける機会はありませんでした。さらに、岡山と大阪・名古屋を行き来する生活をつづけるうちに、自分の気持ちと現実とのあいだの矛盾を感じるようになっていきました。
「そのころ、父親がサラリーマンを辞めて専業農家になって、米づくりの手伝いをする機会があったんです。ほそぼそとですけど、有機農業をやっていて。当時は、いまよりもっと農法が確立されてなくて、ほんとうに手探りだったんですけど、それが面白いんですね。お客さまから直接、よろこびの声、ときにはお叱りの声を聞けることも、嬉しく、励みになって。いい仕事だなと思いました。ちょうど、下の子が産まれるときで、子どもたちには有機農法で育てたお米を食べさせてあげたいという思いもあって。会社を辞めることを決めて、農家に」
そうして、まったく別の道を歩みはじめた山﨑さん。地元、倉敷の田んぼで有機農法の研究と実践の日々を重ね、いまでは二十年近くが経ちます。人のやっていないことをやってみたい。新しいことにチャレンジしたい。山﨑さんはそんな自分のことを「変わり者」だと言いますが、この仕事は彼にとっての天職だったようす。生き生きとしたエネルギーに満ちているようでした。
「晴耕雨読が僕は好きなので、冬場はゆっくりしたらいいんじゃないなんて言いながら……」と山﨑さん。もともと得意としていた鉄工の技術を活かして、お米の倉庫をセルフビルドで建てたり、田植え機や精米機をより使いやすいように造りかえたり、栽培以外の多くのことも、スタッフと一緒に、自分たちの手でやっているそう。「百姓は百個のことができないと」と。

農園の作業小屋の壁には、山﨑さんの掲げる言葉が印字された紙がいくつか貼られていました。なかでも目にとまったのが、「よく考える、常に考える、深く考える」という一枚。
「すべてが、なんでやるの? から始まる。車の設計なら、なんでこの部品がいるの? というところから。それは、たとえば草刈りもおなじです。なんで刈るの? から始まって、どうやって刈るのが一番よいかまで、深く考える。
いまと同じやりかたで、5年後、10年後もやっているとは限らないんです。ただ、有機農業はやっていると思います」
常に変わりゆく環境のなかで、いまの最適解を考える。その柔軟な姿勢が、彼のお米づくりの土台をしっかりと支えています。
岡山で古くから愛されてきた朝日米

できる限りの手を尽くし、おいしいお米を食べてもらいたいという思いから、山﨑さんは、稲刈りのタイミングに人一倍気を配ります。収穫に最も適した期間は、わずか1週間。そのなかで、天候が変わったり、稲が倒伏して条件が変わったりすることもあるので、この時期はとくに気を抜けないそうです。
晩生品種である朝日の稲刈りがはじまるのは、11月に入ってから。ゆっくりと時間をかけて熟し、丁寧に乾燥された朝日は、あっさりとした食べごこちで、お漬物からカレーまでどんなおかずとも合います。よく噛むほどに甘みが感じられるお米です。
「千人に一人でもいいから、その一人に熱烈によろこんでいただけるようなお米を作りたい」
山﨑さんが日々考え抜き、手をかけて育てた「晴れの国の朝日米」。炊きたてのおいしさを味わっていただけたらと思います。
|
晴れの国の朝日米 |
●
季節とともに移りゆく色。
水や土、草花と生きもの。
にぎやかな田んぼの景色を一緒に育んでいきませんか。
おいしいお米を味わうことが田んぼとわたしたちの食卓をむすび、未来につづく農業や暮らしを考えるきっかけとなりますように。