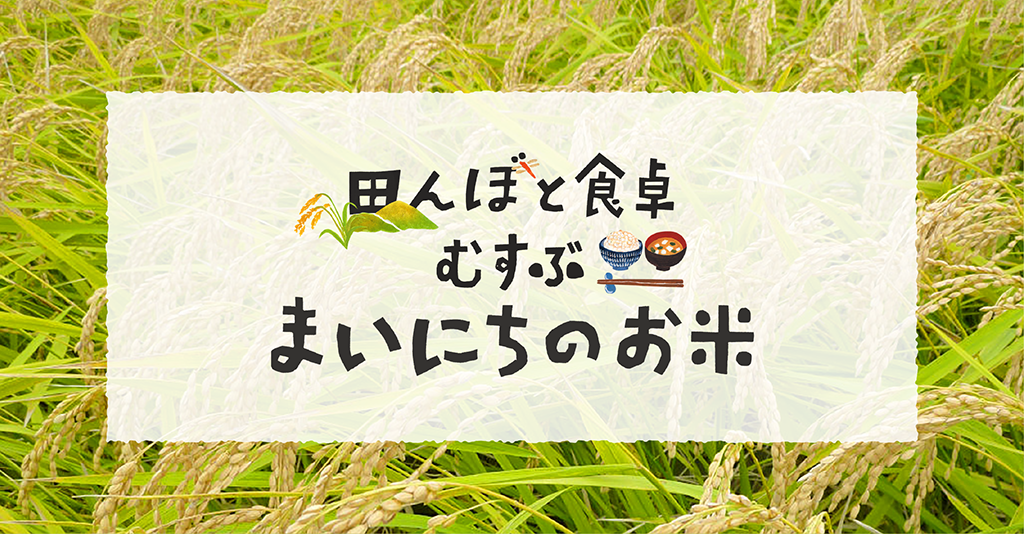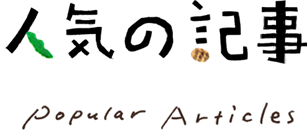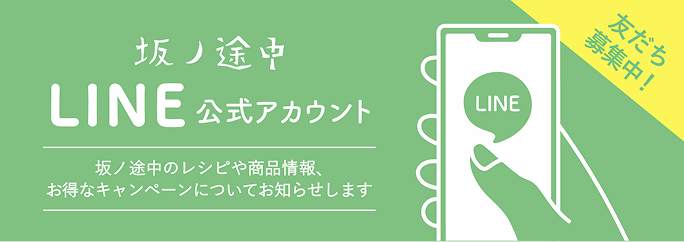気候や土壌と向き合い、環境に配慮して育てられたお米の定期宅配「田んぼと食卓むすぶお米」。
それぞれのお米の産地の景色やつくり手の想い、味わいをご紹介します。
●
多様な生きものが棲む、山の中腹で

山梨県と長野県を南北にまたいで連なる八ヶ岳。その南麓、山梨県北杜市の標高700~800mの中山間地で、株式会社こぴっとの三井勲さんはお米を育てています。
四方を山に囲まれ、八ヶ岳の湧水が直接流れてくるこの地域。山が蓄えた水をお米づくりに活かすことができ、また標高が高いことで昼夜の寒暖差が大きく、作物の味わいにも深みをもたらします。

こぴっとが拠点をおく北杜市の長坂町は、三井さんの地元のまち。八ヶ岳や南アルプスの雄大な山々を間近に感じられる、眺めのすばらしい場所です。長坂町は、名前のごとく町全体が傾斜地になっていて、小さな田んぼが棚田のようにして山の中腹に点在しています。こぴっとがお米を育てる田んぼの数はおよそ270枚。平野の広大な産地とくらべると、作業効率はわるく、水の管理や、土手の草刈りにもとても労力がかかります。
ところが三井さんは、そこに在るものに目を向けました。土手にはさまざまな草が生え、虫たちがあつまり、多様な生態系がつくられていることに気付いたのです。周辺には絶滅危惧種のナミゲンゴロウも。ここに棲むたくさんの生きものは、お米が自然豊かな環境で育っていることを証明してくれている。そう考えた三井さんは、この価値をひろく伝えていくために、水田環境を数値で評価できる鑑定士の資格も取得。20年近く、環境への負担の小さい農業をつづけてきたことで、生きものの数や種類はさらに増えてきているといいます。

この地域で100年、200年つづく農業を。

三井さんが地元に帰って農業をはじめたのは、2008年、23歳のころ。就職した会社での仕事にも慣れ、ゴールまでの道のりが見えたように感じていたとき、兼業農家でお米づくりをしていた父と母のすがたを見て、心が動きました。
「農業はゼロからはじまるものづくり。土に種を蒔き、世話をして、それを自分自身で商品として販売するところに面白みを感じた」と三井さん。それからすぐに会社員を辞めて、実家のお米づくりに加わることに。
はじめは面積も小さく、経営が安定せず、厳しいことや悔しいこともたくさんありました。それでも徐々に農地の面積を増やし、助けてくれる人たちにも出会い、いまでは法人化。土地の自然をまもりながら農地を活用することは、地域貢献にもつながっています。

農業という仕事を、いまはどのように捉えているのでしょうか。
「まず、やっていて面白いというのが一番。そして毎年毎年あたらしく種を蒔いて、植物と対話しながら――稲の葉っぱのかたさだったり、色だったり、穂が出るのが早いねとか遅いねとか、穂の長さが今年はちょっと短いかなとか――、その年の天候にあわせて、考えて動く。よい年もあれば、わるい年もあるからこそ糧になり、ゴールがないですね」
会社名の「こぴっと」は、山梨の方言で「しっかり」や「ちゃんと」という意味。「こぴっとしろ、こぴっとしろ」と、よくおばあちゃんに言われていたことから、その言葉の響きと、ちゃんとしたものづくりをしようという想いを込めて、名付けたそうです。
米作りはすべての原点。地域に必要とされ、100年先も、200年先も残るようなかたちで、しっかりと農業を続けていける会社をつくりたいというのが、これからの目標です。

お届けするお米
こぴっとの五百川
五百川は、コシヒカリのなかでとくに生長の速い稲を選抜して品種登録された、早生品種のお米。植え付けから収穫までの期間が短く、8月には稲刈りをむかえますが、味が落ちにくく一年を通して楽しめます。
味わいは、甘みがありながらすっきりとしていて、どのようなおかずにもよく合います。冷めてもおいしく、お弁当向けにも喜ばれているそうです。
「いちど食べて、また食べたいなと思っていただければ一番です」と三井さん。
毎年の楽しみにしていただけたらうれしいです。

|
こぴっとの五百川 特別栽培農産物相当(化学合成農薬の使用成分回数、化学肥料由来の窒素成分量が栽培地域で慣行的に使用されているものの半分以下) 坂ノ途中の特別栽培についての考え方はこちら |
●
季節とともに移りゆく色。
水や土、草花と生きもの。
にぎやかな田んぼの景色を一緒に育んでいきませんか。
おいしいお米を味わうことが田んぼとわたしたちの食卓をむすび、未来につづく農業や暮らしを考えるきっかけとなりますように。