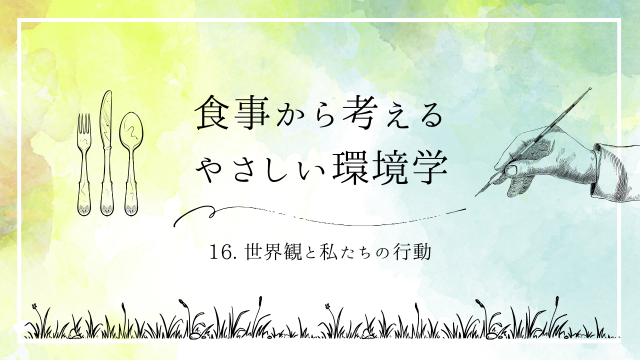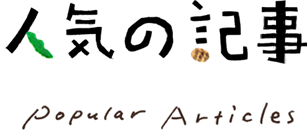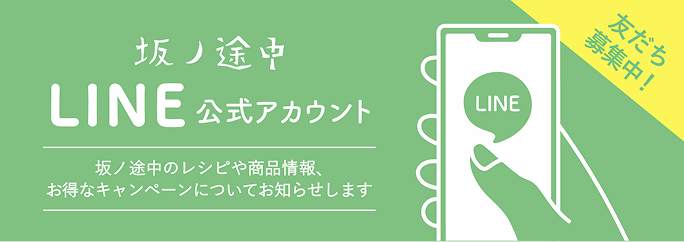5月、6月の連載記事で、「世界観」の話をしてきました。
話のきっかけは、日本の食生活でした。日本は、過食や肥満が少なく、肉の摂取量も少ない国です。こうした食生活を、私たちはさほど意識することなくしています。
では、なぜ日本にそのような食生活が根付いているのでしょうか? その背景には世界観があると私は考えています。だからこそ、この連載では「世界観」についてお話してきたのです。
とはいえ、世界観というのは、なかなかわかりにくいものです。そもそも、「世界観」はどうやって私たちの行動に影響を与えるのでしょうか? さらに、私たちは「世界観」をどう身につけるのでしょうか?
今回は、これらの問いに答えてみようと思います。そのことを通して、世界観について深く知っていただけたらと考えています。
まず、「世界観」と私たちの行動の関係について考えましょう。大事なのは「世界観は、私たちの意識が働く前に行動を規定する」という点です。
たとえば、私の家族が病気になったとします。すると私は心配になり、きちんと水分を摂らせたり、薬を飲ませたりします。
このとき、私が意識的に考えているのは、「今、水分は足りているかな」「どんな薬が必要かな」といったことです。
ですが、その手前に「家族のことが心配になる」という段階があります。これは意識して考えた結果ではありません。気づいたときにはもう心配していて、行動を始めているのです。考えてみると、実に不思議なことです。

なぜこんなことが起きるのでしょうか? それは「家族と自分が重なりを持っている」という相互依存的世界観を、私が持っているからです。だから、家族の苦しみは同時に私の苦しみでもあるのです。そう考えると、家族が病気になったときに、「意識をする前にすでに行動している」というのも納得がいきます。
このような「世界観」こそが、環境問題の根本だとする考え方もあります(たとえば、歴史学者リン・ホワイトや哲学者アルネ・ネス)。人間は自然から離れ、自然に対して「重なり」を持たなくなった。そのため、自然の苦しみを自らの苦しみとして感じられず、必要な行動をとらなくなった。こういう考え方です。
この観点からすると、日本は興味深い国です。というのも、日本には今もなお、自然との重なりを感じる人がある程度存在するからです。実際、日本には「食べ物をいただく」という感覚が一般的に存在し、食事を残さないよう、適量盛り付ける傾向にあります。これが、日本で過食や肥満が他国と比べて少ない一因だと、私は考えています。
さらに言うと、日本は国際的に見てフードロスの少ない国です。World Population Reviewの2024年の統計によると、日本の一人当たりのフードロスは、英米豪などアングロサクソン諸国より少なく、多くのEU諸国よりも少ないようです。この背景にも、自然との重なりを感じる相互依存的世界観があると、私は思っています。
では、この相互依存的世界観を、私たちはどのように身につけるのでしょうか? それは、日々の生活実践を通してです。
たとえば、食事の前に「いただきます」と言って、自然や農家さん、料理を作ってくれた人に感謝を表す。この行為を通じて、私たちは、自然や他の人々との関係性と重なりを日々確認しています。

これはわかりやすい例ですが、私たちはもっといろいろな生活実践をしています。
日本の幼稚園の給食の時間、子どもたちがニンジンを残しているのを見て、先生はこう声をかけました。「ニンジンさんも食べてあげないと、悲しいんじゃないかな。」
このひと言で、子どもたちは「自分の行為によってニンジンさんが喜んだり悲しんだりする」と感じます。つまり、子どもたちはニンジンさんとの間にある関係性と重なりを感じるようになります。
この事例は、日本で育った人には当たり前すぎて、つい見逃してしまいそうなものです。ですが、アメリカで育ったジョセフ・トービン先生(アメリカ・ジョージア大学,幼児教育の世界的権威)は、この事例を日本の幼稚園で見出し、とても驚いたそうです。ニンジンさんの気持ちに思いを馳せるというのは、トービン先生の育った文化には、ほとんど見られない考え方だったからです(Tobinら『Preschool in Three Cultures Revisited』)。
こういう小さな生活実践が積み重なって、私たちの世界観は形成・維持されているのです。だからこそ、日々の暮らし方はとても大事だと私は思っています。
けれど、生活実践が世界観へ影響を及ぼすというのは、本当でしょうか? 証拠はあるのでしょうか? 次回は、この点について考えてみましょう。それでは、また。
![]() 小松 光(坂ノ途中の研究室)
小松 光(坂ノ途中の研究室)