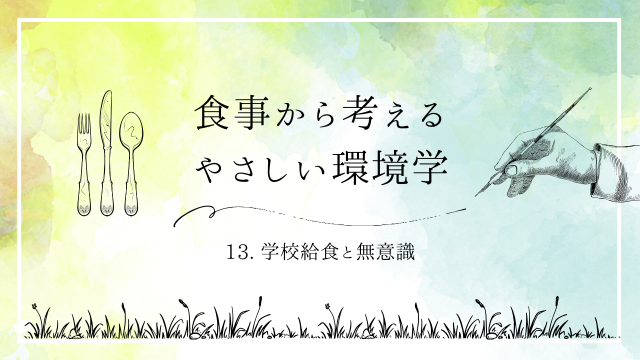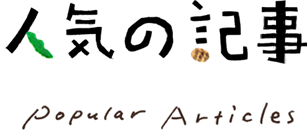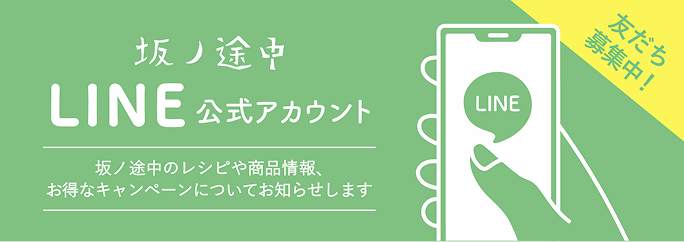日本の肉の消費量は、なぜ少ないのだろう? そういう問いを、先月、提示してみました。
日本人の多くは、肉食を減らそうと意識的に努力しているわけではありません。また、今の日本人の多くは、肉食に対して、強い忌避感を持っているわけでもありません。実際、菜食主義者の割合は、他の高所得国と同程度です。ですが、なぜか一人当たりの肉の消費量は少ないのです。
なぜそうなのか? 理由を考えつきますか?
もちろん、理由はたくさんあるはずですが、私はその一つとして、学校給食を挙げたいと思います。
日本の学校給食には、驚くべき特徴があります。メニューを選べない、という特徴です。
「学校給食でメニューを選べない」というのは、この記事を読んでいるほとんどの人にとっては当たり前かと思います。でも、世界では当たり前ではありません。
昼になったら各々がカフェテリアに行って、自分の好きなものを食べる国もあります。日本と同じように教室でみんなで給食を食べるけれど、食べ物はバイキング形式で自由に選べる国もあります。多くの場合、自分の意思で食事をある程度決定することができます。

でも、日本の給食ではメニューを一切選べません。さらに、学内に売店も自販機もないのが一般的ですし、家から食べ物を持ってくるのも、アレルギーなどの事情がない限り認められません。つまり、日本の学校において、子どもたちは食事への決定権を持っていないのです。
こういう生活を少なくとも小学校6年間、そして多くの場合、小中学校9年間続けるのです。幼稚園や保育園で給食が出る場合には、その期間はさらに長くなります。これは、すごいことです。
少し余談になりますが、先日、アメリカ・オレゴン州にある大学の大学生と先生が、坂ノ途中を訪れる機会がありました。そのときに、日本の学校給食の話をしたうえで、食事への決定権がない生活に耐えられるか、尋ねてみました。
多くの学生は難しいと思ったようです。とくに、家から食べ物を持ってきてはいけない、というのはショッキングだったようです。そんなことまで制限されるというのは、おそらく不当なことに映るのでしょう。たしかに、学校を学業の場と捉えるなら、食事などは学業と無関係なので自由にすべきだ、という考え方があっても不思議ではありません。
話を元に戻しますが、この学校給食が、日本人の肉の消費量の少なさの主要な原因の一つだと、私は思っています。というのも、食事への決定権がない生活を続けることを通じて、子どもたちは「適切な食事とはどんなものか」を学ぶからです。たとえば「食事の適切な量とは、どのくらいなのか」「肉・魚・野菜の適切なバランスはどのくらいなのか」などを、無意識に学んでいるわけです。
その結果、大人になっても、肉が多量に使われている食事に対して、なんとなく違和感を持つわけです。たとえばアメリカなどに行けば、一食で肉を300グラムくらい使う料理は、珍しくありません。そういう食事を出されると、多くの日本人は「ちょっと肉の量が多すぎる」と感じるわけです。

日本は肉の消費量が少ないだけでなく、肥満率も驚異的に低いのですが、これも学校給食によってかなり説明できそうです(学校の授業で体育が多い、という理由もあるのですが)。実際、子どもの肥満率が低い国では大人の肥満率も低く、子どもの肥満率が高い国では大人の肥満率も高い傾向にあります。つまり、子どものころの食習慣が、大人の食習慣の土台になっているのです。
ここまで、私たちはあまり意識していないけれども、日本の学校給食が日本人の食生活を規定している、という話をしてきました。
ですが話はこれで終わりではありません。そもそもなぜ、日本の学校給食ではメニューが選べないのでしょうか? このことについて、次回お話しさせてください。それでは、また。
![]() 小松 光(坂ノ途中の研究室)
小松 光(坂ノ途中の研究室)