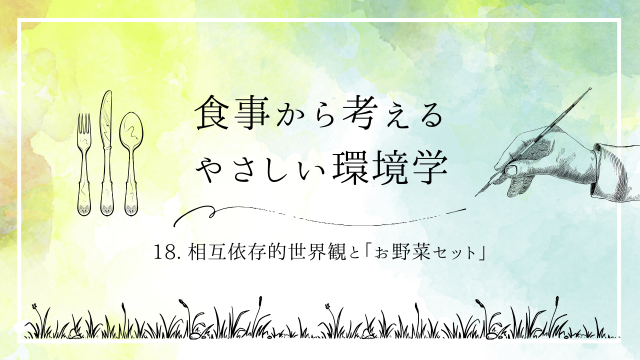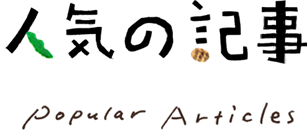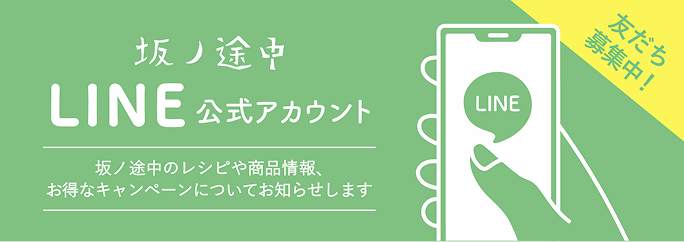前回はこんなお話をしました。私たちは、日々さまざまなシグナルを受け取りながら世界観を形づくり、それを維持している。そして、その世界観が、意識の前段階で行動に影響を与えている。
たとえば小学生は、学校給食や班活動を通じて「相互依存的世界観」を育んでいます。「相互依存的世界観」とは「自分と他者の間に重なりがある」という感覚のこと。この感覚が、日本で過食やフードロスが少ない理由の一つになっていると、私は考えています。
では、給食も班活動もない大人は、どうやって相互依存的世界観を保つことができるのでしょうか。
私は、坂ノ途中の「お野菜セット」がそのヒントになるのではないかと思っています。長らく大学などで研究者として過ごしてきた私がこの会社に入社したのも、そんな思いがきっかけでした。「なんだか面白そうなことをやっている会社だな」と感じ、中から見てみようと思ったのです。
以下、坂ノ途中の「お野菜セット」のことを書いていきますが、「お野菜セット」の宣伝がしたいわけではありません。私の狙いは、「お野菜セット」というサービスを分析することで「相互依存的世界観を維持する実践のヒント」を知っていただくことにあります。
「お野菜セット」は、旬の野菜を詰め合わせて、お客さまに定期的にお届けするサービスです。お客さま自身が野菜を選べないのが特徴で、これは給食のメニューを自分で選べないのと少し似ています。

こうしたサービス自体は昔からありますが、私が驚いたのは、不便にも思えるこのサービスを多くの方が利用していることでした。私が入社した時点で8,000世帯、今では12,000世帯ものお客さまが利用されています。
その理由の一つは、お野菜セットが「商品」ではなく「贈り物」になるように工夫されているからだ、と私は思っています。
お野菜セットには「お野菜の説明書」が同封されています。そこには野菜の特徴や料理法、そして、生産者さんのお名前が書かれています。さらに、お客さまは食べた感想を生産者さんにフィードバックすることもできます。
これは、旅行のお土産を友達に渡す場合に似ています。お土産を選ぶのはあなたであって、友人ではありません。あなたはお土産を渡すときに、きっとそのお土産について説明をするでしょう。次にあなたが友人と会ったとき、友人はお土産の感想を教えてくれるかもしれません。「贈り物」とは、モノそのもの以上に、人と人の関係をつなぐものなのです。
お客さまの中には、お野菜セットを生産者さんや自然からの「贈り物」と捉えてくださる方がいるようです。お客さまアンケートでも「何が届くかわからないのが楽しい」という声をいただくことがあります。
もちろん、自ら選んでいない野菜を調理するのは簡単ではありません。見慣れない野菜や、一本まるごとのダイコンを前に「どうしよう?」と戸惑うこともあるでしょう。そこで坂ノ途中では、珍しい野菜のレシピや、ダイコンの部位ごとの調理法などを紹介しています。こうすることで、お客さまに生産者さんや自然からの贈り物を楽しんでいただけたら、と思っているのです。

少し「おせっかい」な会社かもしれません。でも、その「おせっかい」こそ、相互依存的世界観を支える実践なのだと、入社してからの2年で感じるようになりました。私自身は、お野菜セットの特徴を知ったことで、スーパーマーケットでのお買い物に変化が現れました。
たとえばお野菜を選ぶとき、できるだけ生産者さんの情報が書かれているものを選ぶようになりました。そしてお野菜の育てられた農園の場所や周囲の自然について、調べてみたりもします。さらに、旅行などのときに、農園の周辺まで行ってみることもあります。
ほかにも、いつも同じ野菜を買うのではなく、ときには今まで買ったことのない野菜を買うようになりました。生産者さんや自然からの贈り物を上手に楽しめるように、料理の技術を上げたいと思ってのことです。
こうした工夫によって、給食も班活動もない大人も、相互依存的世界観を保つことができるのではないか、と私は思っています。
ここで紹介した生活実践は、それ自体とてもささやかなものです。でも、それが自らの心を少し変え、その変化がまた別の人に伝わり、やがて社会全体を変えていく。そんな風になるといいなあ、と思っています。
![]() 小松 光(坂ノ途中の研究室)
小松 光(坂ノ途中の研究室)