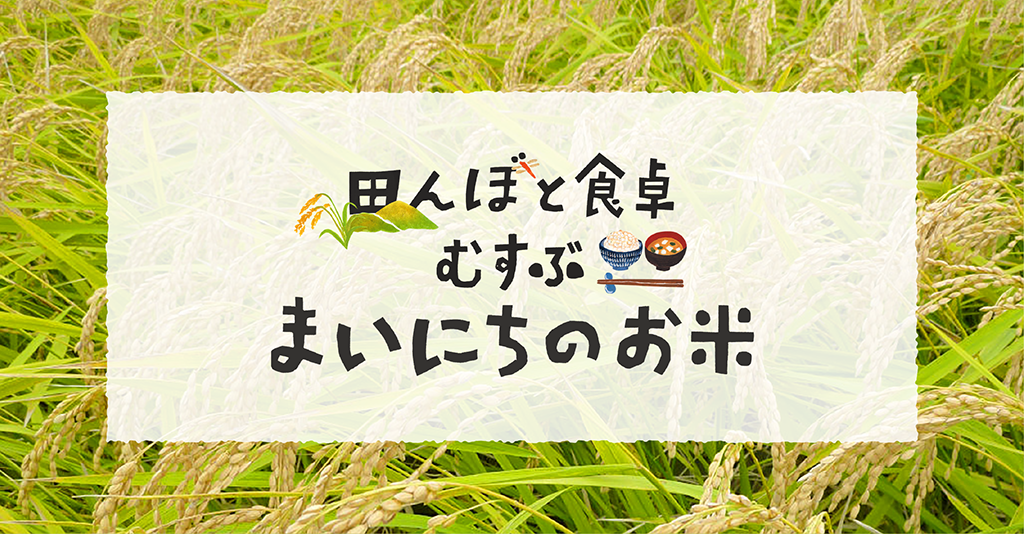あっさりながら、甘味とうまみしっかり

山と湖の景色が広がる、水の豊かな米どころ、滋賀。ここに伝わる「滋賀旭」の種を繋ぎ、宝のように大切に育てられてきたお米を、滋賀県草津市のクサツパイオニアファームさんからお届けします。

「湖国のたから米」と名付けたこのお米は、やや大粒であっさり。滋味深い甘みとうまみは、毎日でもお箸がすすむ味わいです。昔ながらの品種で、とくに梅干し、海苔、お味噌汁といった日常的な和食によく合います。粘りがひかえめで、味なじみがよいので、ちらし寿司や巻き寿司などにもおすすめ。ハレの日にも、ケの日にも、寄り添ってくれる、そんなお米です。
種とりをつづけて二十年、滋賀在来のお米

クサツパイオニアファームさんがその種を繋ぐことになったきっかけは、約二十年前の、地元のお米屋さんの話から。ある農家さんで頂いたご飯がえらくおいしかったそうで、聞くとそのお米は当時すでに世間に出回っていない品種。味がよいからと農家さんが自家用に育てていたものでした。お米屋さんは、この地で親しまれてきたおいしいお米を広めたいと、当時の代表に話を持ち掛けたのです。
「ほんの十粒ほどの種を譲り受けたところから、これまで約二十年、種籾を自ら採って、有機栽培の田んぼで育ててきました。今ではより、この地の土壌に合った種になってきています」と、代表の中山欽司さんは言います。
稲のもつ力を生かし、地域の資源や生き物を大切にする農法

昔ながらのお米は、収穫時期が遅かったり、機械での収穫に向いていなかったりと、生産者さんにとっては不利な面もあります。けれど、クサツパイオニアファームさんの田んぼでは、毎年少しずつ、栽培量を増やしています。
理由は、味がよいのはもちろん、稲の生命力がつよく、化学合成農薬や化学肥料に頼らない農法でもよく育つから。どこか野性的で、草との競合や病害にも負けにくいのだそう。
自然のままに稲の力を生かし、また、田んぼやそのまわりに棲む生き物たちともうまく付き合いながら、健全においしく育つ農法を追求しています。
稲作から生まれる副産物の「もみ殻」や「米ぬか」は、自社で堆肥化させ、田畑の土づくり資材として再利用。地域の資源を活用し、循環型農業を行っています。
たとえば、米ぬかはペレット状にして、田植え後の田んぼに撒きます。これにより、草を抑えるとともに田んぼの微生物を増やし、肥料分を補うこともできるのです。
おいしいお米、美しい景色、まちづくり

滋賀県南西部、琵琶湖のほとりにあり、古くから交通の要所として栄えた街、草津。
クサツパイオニアファームさんの田畑は、そのいちばん山ぎわの地域、馬場町(ばんばちょう)にあります。初夏には蛍のとぶきれいな水が流れ、穏やかな田畑が広がる地域。ここで彼らはあわせて50ヘクタール以上の、大きな農地を任されています。
「自分たちが育てる作物の種類や育て方によって、町の景観をどんな色にも染めることができる」。そう考える代表の中山さんは、環境負荷の小さい農法でおいしい作物をつくることだけにとどまらず、観て美しい田畑、心地よい景色をつくることをも心がけています。

絵を描くように育てる赤紫蘇や赤米、田んぼの水面や稲穂が織りなす春夏秋冬の風景には、人びとが引き寄せられるように集い、町はにぎやかに。
「美しい景色があれば、人が集まる。人が集まれば、町が元気になる」
この町で人びとの暮らしがつづいていくことを願い、農業というかたちで表現する。そんなふうに、明るい地域の未来を思い描く中山さんの周りには、多くの仲間が集まっています。

ご注意点
■玄米の調製年月日について
玄米には裏面の品質表示ラベルに農家さんがもみすり(稲もみからもみ殻を取り除いて玄米にする作業)をした日付「調製年月日」を記載しております。調製年月日には稲刈りのころの日付が記載されていることがほとんどです。
玄米は、白米と違って、適切な保存状態であれば長期保存してもほとんど劣化しませんので、調製年月日から時間がたっていても品質には問題ございません。
■小石や種の混入について
丁寧に選別はしているものの、稲刈り時の小石や、クサネムと呼ばれる雑草の種(小さな黒い粒)がお米に混ざってしまうことがございます。
お米の品質には問題ございませんので、お米を研ぐ際に取り除いてお召し上がりいただければと思います。気になるような状態でしたら、お手数ですがご連絡くださいませ。
■お米の保存について
お米の保存は、風通しがよく、直射日光のあたらない、15度以下の場所が適しています。
倉庫の管理や選別機でのチェックを丁寧に行っていますが、まれに「コクゾウムシ」と呼ばれる虫がお米の中に入り込んでしまうことがございます。気温が20度を超えると活動が活発化するので、気温・湿度が高くなる時期には、特にお米の保存場所にご注意ください。
季節や温度を気にせず、お米をおいしく保つことができる場所は、冷蔵庫の野菜室です。におい移りを防ぐため、ペットボトルや密封できる容器に入れて保存し、お届けから30日を目安にお召し上がりください。
品質に問題がある場合は、商品到着後30日以内にご連絡いただきますようお願いいたします。それ以降は、ご返金や再送の対応は難しくなりますので、予めご了承くださいませ。
田んぼと食卓むすぶ まいにちのお米
お米が育つ背景や、その豊かな味わいについてもっとお伝えしたい。そんな思いを込めて、「田んぼと食卓むすぶ まいにちのお米」というお米の特集ページをご用意しました。
おいしいお米を味わうことが、田んぼとわたしたちの食卓をむすび、未来につづく農業や暮らしを考えるきっかけとなりますように。