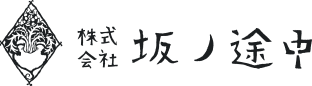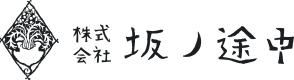基準、作ってみました。
新しく農業をはじめた人たちが、化学合成農薬や化学肥料を用いずに育てた農産物を扱おう。
そんなおおまかな方針を頼りに坂ノ途中は歩んできました。
でも、気づけば40人を超えるスタッフを抱えるまでになりました。
大雑把でいいの?とか、なにを「化学合成農薬」と呼ぶの?とか、
スタッフのなかでも話し合いになることがあります。
だから少しずつでも基準を明確にしていきたいと思っています。
もちろん基準を作って終わり!にはしたくはありません。
農業はきわめて多面的な機能を持っています。角度によって見え方がまったく異なります。
栽培技術は日進月歩だし、新しい意見も次から次へと飛び出してきます。
原理原則を大切にしつつ、常に見直しを図ったり、議論したりすることが大切だと思っています。
というわけで、この基準はあくまで暫定のものです。
このあたり、どう考えてるの?それっておかしくない?
そんなご意見もお待ちしています。 ≫加工品の取り扱い基準 ≫放射能に対する取り組みはこちらをご覧ください。
そんなご意見もお待ちしています。 ≫加工品の取り扱い基準 ≫放射能に対する取り組みはこちらをご覧ください。
取り扱い基準
基準01

環境負荷の低減を目指す
農家さんを優先します。
- CO2やメタンガスなど、温室効果ガスの排出を低減する
- エネルギー効率の改善に取り組む(化石燃料や化学肥料への依存度を下げる)
- 限りある資源に頼らない(リン鉱石やカリ鉱石、天然ガス、石油、ピートモスなど)
- 生物多様性の維持、回復に取り組む(多くの生き物の生息地となるような冬期湛水や魚道設置などの工夫、 インパクトの大きな農薬の不使用、GMO種子の不使用)
- ローカルな余剰有機物を利活用する(近所の養鶏場からもらってきた鶏糞のたい肥化、落ち葉や畔草の利活用など)
- カバークロップや緑肥の活用による土壌流亡の抑制