甘みをたくわえた、春のアスパラガス

九州の暖かな海に囲まれた長崎・島原半島から、やわらかで甘みのある、春のアスパラガスをお届けします。
アスパラガスは冬のあいだ、根や地下茎に養分をたくわえ、春、暖かくなると地上に芽を出します。通常は年に2回、春芽と夏芽の収穫がありますが、春芽はとくに甘みたっぷりで、青々と香り豊か。穂先はほっくり、根元はしゃきしゃきの食感が楽しめます。
農家さんのおすすめの食べ方は、そのまま素揚げや炭火焼きにして、お塩をぱらり。シンプルな調理でアスパラガスの風味がさらに引き立ちます。
今だけの、みずみずしい春の味をお楽しみください。
暖かな陽のあたる南島原で、すこやかに育てる

三方を海に囲まれ、中央には雲仙岳がそびえる、長崎県南部の島原半島。
長崎有機農業研究会の松尾和昭さん、康憲さん親子は、半島の一番南側、南島原市でアスパラガスの栽培をしています。
アスパラガスは、たった1日で15cmも伸びることがあるほど、生育旺盛な野菜。この生長を支えるためには、肥沃な土壌と、たっぷりの水と、太陽のひかりが大切です。山の水に恵まれ、半島の南端で日照時間が長い南島原の土地は、おいしいアスパラガスが育つ条件が揃っています。
もともとは粘土質だという松尾さんの畑の土。水や肥料のもちは良いけれど、固くなりやすい土質でもあります。そこで、牛ふん堆肥やもみ殻などの有機質肥料をすき込んで、やわらかく、通気性が良くなるよう手を入れています。投入した肥料分は、土のなかの微生物が分解し、アスパラガスの養分に。肥料分のバランス、菌(微生物)がはたらく環境をととのえることで、味わいも良くなります。
つくり手のこと
長崎有機農業研究会 松尾和昭さん 康憲さん(長崎県南島原市)
アスパラガスを育てているのは、主に息子の康則さん。2001年、二十歳で就農しました。農業を営んでいる父、和昭さんが身体を動かしながら働く姿が楽しそうで、この道を選びました。
長崎有機農業研究会の立ち上げメンバーのひとりである和昭さんの想いを引き継ぎ、環境負荷の少ない農法で、アスパラガス、玉ねぎ、じゃがいもなどを育てています。
アスパラガスは、一般的な栽培方法では、5、6年で株を植え替えることが多いのですが、松尾さんの畑では、20年以上育てているものも。株を休ませたり、有機質肥料を漉き込むなど、土づくりを工夫することで、長年収穫ができています。
「大変なことも多いですが、食べてくれる方の笑顔を想像すると頑張れます。収穫の瞬間は何よりの楽しみ。苦労した分だけ成果が実り、自分に返ってくるのがこの仕事の醍醐味です」
松尾さんの畑があるのは、地域では上晴山(うわはるやま)と呼ばれている小高い場所。南側には島原湾が広がっています。「畑から見下ろす海、いい景色ですよ。農作業をするには気持ちのいい場所です」と話してくださいました。
アスパラのおいしいレシピ
また手にとりたくなる野菜について
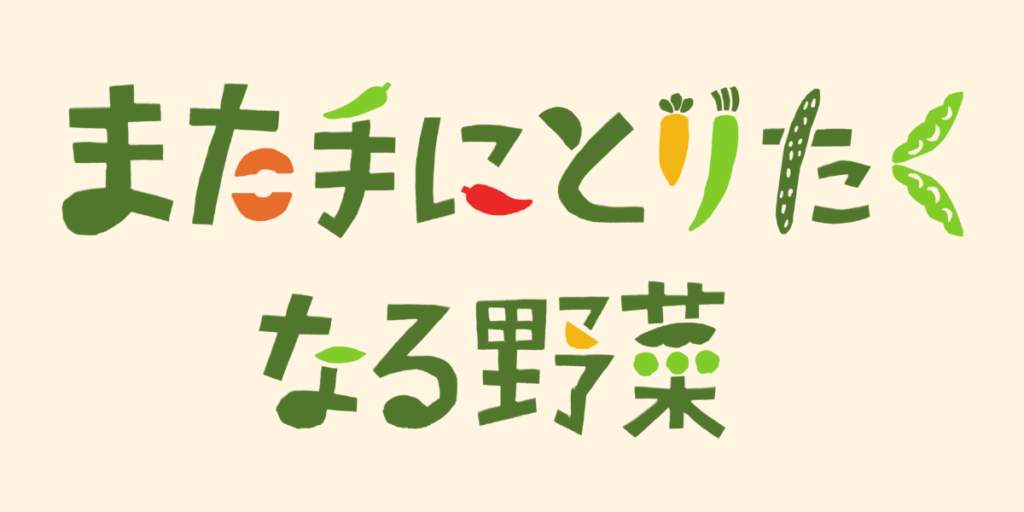
美味しく育つ、理由がある
日本の風土は多様です。
暖かな風と日光に恵まれたところ、ずっしりと雪が降り積もるところ、豊かな森と海に囲まれたところ――。
気候や地形、土壌によって、育つ作物もさまざまです。
その土地の特長を生かしながら、手をかけて育てられたお野菜は、うんと美味しい。
たとえば、瀬戸内海の無人島で日光をたっぷり浴びたまろやかなレモン、鳥取・大山のジンジンとする寒さのなかで甘みの増したキャベツ、対馬の海風を受け栄養を蓄えた原木で育った香り高いしいたけ。
「また手にとりたくなる野菜」では、そうした、美味しい背景、ストーリーをもったお野菜やくだものをお届けします。お料理をつくりながら、食卓を囲みながら、「農家さんはこんな人なんだって」「こういう場所で、こんな工夫で育てられているんだよ」「また食べたいね」そんな会話のきっかけにもなれば、とても嬉しいです。












