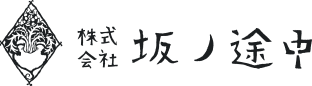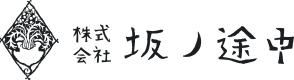栽培基準とその運用について
私たちは弊社ホームページの「基準01/環境負荷の低減を目指す農家さんを優先します」で、取り扱うお野菜やお米の栽培基準を下記のように定めています。
「セットにお入れするお野菜とお米は栽培期間中、化学合成農薬、化学肥料は原則不使用です。」
2019年7月に「原則」という言葉を書き加えました。
「原則不使用」とした理由
お届けするセットのお野菜は、栽培期間中に、化学合成農薬、化学肥料を使用していないものとする。その考えはこれまでと変わるところはありません。
けれども、「絶対に不使用です!」と言い切ることは、実はとても難しいのです。
お野菜の栽培履歴を、出荷作業のたびにすべてチェックすることが不可能だからです。
オーガニックの難しさ
私たちのルールはシンプルなものです。お野菜の栽培に化学合成農薬、化学肥料を使わない。生産者さんはそのルールに則ってお野菜を育てています。
問題は、そのルールが、なんだかとても守りにくくなっているところにあります。
たとえば、ホームセンターや資材店で販売されている肥料ですが、「有機原料」「有機肥料」などと記載されていても、すべてが有機肥料というわけではありません。単に「有機入り」というものを見かけます。原料のなかに有機質由来ではない物質が含まれていて、とくに肥料成分の中心となる窒素は、化学合成されたものが使われていたりします(もちろん、それらの肥料がなにかの問題を抱えているわけではありません。あくまで弊社の栽培基準からは外れている、というお話です)。
そしてときには、成分の確認がとても難しいものがあります。
各地の堆肥センターで作られる堆肥は100%有機のはずです。ところが、原料のなかには、食品加工工場から出されるサトウキビの搾り液の発酵滓のようなものがあります。肥料としては優れたものですが、発酵の過程でpH調整のために尿素のような化合物が混ぜられている。尿素そのものは食品として使用が認められていても、化学合成物質です。この肥料を用いて育てたお野菜は有機JAS農産物とは認められません。私たちは、そのような肥料を使用しないよう注意を喚起してきましたが、肥料の原料を作る過程で化学合成物質が用いられているケースは非常に判別が難しく、その情報は肥料袋にも製造元のホームページにも記載されていないことが多いため、把握しきれないのが現状です。
栽培履歴のチェックについて
坂ノ途中は、リアルタイムでの資材(※)のチェックは行わないという方針をとっています。
私たちのところには、毎日100軒の農家さんから200種類を超える野菜が届きます。そのすべてを常に資材チェックして出荷しようとすると、私たちにも農家さんたちにも、膨大な手間(コスト)が必要になります。そして、時間がかかってしまう分、鮮度も落ちてしまう。
パートナーとなってくれた農家さんは、就農されて間もない方、1〜2人で営農している方が多くいらっしゃいます。そんな人たちに、毎回の栽培履歴の提出を強いることは、大変な労力を割かせることになる。
農家さんたちの、珍しい品種のお野菜を育てよう、よりよい栽培方法を試してみよう、そんな挑戦を私たちが後押しすることも、楽しむこともできなくなる。「手間が余計にかかることはやめてほしい」「もっと品種を絞ってほしい」なんて無粋で窮屈なことを押し付けてしまうかもしれません。
あまりに過剰なチェック体制は、私たちや生産者の時間を奪い、コストを上げ、お野菜の品質や面白さを失わせることになる。私たちはそう考えています。
私たちは、年に一度、生産者さんたちから、圃場で使用する資材のリストを提出してもらい、内容の確認を行っています。
そのうえで、すべての生産者さんたちと「この資材は〇〇なので、基準から逸脱してしまいます」「まぎらわしいけれど、この資材は大丈夫です」そんなふうに情報を共有しています。
この作業は、私たちにとって、また生産者さんたちにとって、とてもよい勉強の機会になっています。
坂ノ途中の目指すところ
坂ノ途中のメッセージは「100年先もつづく農業を」。
私たちの目的は、農業を持続可能なものとする、
そうして社会が持続可能なものへとなっていくということです。
栽培基準というルールは、そのための手段のひとつ。
ですから、ルールを守ることを大切と考えながらも、
べつの視点でルールそのものを問い直す、
検証する作業も常に行っています。このルール(手段)
は間違いのないものだろうか?
特別栽培の青果物の取り扱いをどう考えるか(
※詳しくはこちらをご覧ください)もそのひとつです。
先に述べた尿素の問題にしても、
廃棄される有機物を有用な肥料にできる、
資源の循環を実現できるという点では、使用を禁止すべきか、
許容すべきか、迷うところです。いまのところ生産者さんたちには、「使わないでください」とお伝
えしていますが、そのルールは変わるかもしれません。
そしてもうひとつ。
ルールを逸脱するようなミスがあったとしても、そのことで、
これまで一緒に歩んできた、お客さま・農家さん・
私たちが切り離されるようなことがあってはならないと考えていま
す。
私たちが目指すところにたどり着けるよう、みなさまにはご理解、ご支援をいただければと思います。
2019年8月1日 株式会社 坂ノ途中
栽培基準を管理するためのガイドライン
①年に一度、圃場で使用する資材リストを提出してもらう。
(資材内容の確認・共有を行う)
②出荷前に、その都度の栽培履歴の提出は行わない。
(お手元に届いたお野菜や果物の栽培履歴を確認したい方は、お問い合わせフォームより連絡をくださいませ。1~2日ほどで生産者さんに履歴を提出いただき、ご回答いたします)
③特別栽培同等の栽培基準である果物類は、出荷前に栽培履歴の確認を行う。
(特別栽培農産物の基準に則っているか、確認が必要なため)
④栽培基準の逸脱が発見された場合、その内容、経緯について、お客さま、各生産者に向けて即時に報告する。
安全性等について疑念のある場合は、野菜果物の内容を専門機関にて分析し、その結果を報告する。
※農業生産資材のこと。ビニールハウスや除草シートのようなものだけでなく、肥料や農薬も資材にあたります
坂ノ途中の栽培や基準についての考え方 一覧
「いまのところの」取り扱い基準
特別栽培についての考え方
放射能に対する取り組み
栽培基準とその運用について