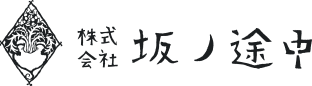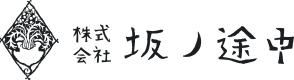坂ノ途中は2025年1月18日(土)に、お客さま向けの体験イベントを初めて開催します!
坂ノ途中は2025年1月18日(土)に、お客さま向けの体験イベントを初めて開催します!
当日は、坂ノ途中スタッフや提携生産者とのお話会や試食会など、さまざまなプログラムをご用意しております。ご友人やご家族とぜひご参加ください。
■お野菜の試食会
家庭ではなかなかできない、いろいろな品種の食べ比べ。今回は「大根」と「じゃがいも」をご用意しました。定番のものから、スーパーではあまり見かけないものまで、お試しいただけます。

(例)紫だいこん、紅だいこん、黒丸だいこん、青首など
また、坂ノ途中で取り扱っているお味噌やお醤油、マヨネーズなどの調味料もご用意。お野菜と一緒にご自由にお試しいただけます。
■坂ノ途中スタッフの講演

「食事から考えるやさしい環境学」をテーマにコラムを執筆している小松と、お野菜セットの組み合わせを毎週考えている三牧・平石が、坂ノ途中で取り組んでいることについてお話します。
普段、お客さまからは見えない裏側のストーリーをお伝えできればと思います。
■提携農家さんとのお話会

坂ノ途中と提携している農家さんと気軽にお話ができる時間も設けております。おいしいお野菜の食べ方や農業のことなど、疑問に思っていることや気になっていることを質問してみてくださいね。
また、3人の農家さんからお土産も。1世帯につき1セットお持ち帰りいただけます。
<お土産の内容>
・キセツノオヤサイ葉屋さんの「クッキー」
・べじたぶるぱーくさんの「大葉ソルト」
・フードハブ・プロジェクトさんの運営するパン屋・かまパンさんの「いつもの食パン」
「農家さんのお話を聞きたい」「坂ノ途中スタッフと話してみたい」「お野菜の食べ比べをしてみたい」など、少しでも興味のある方はぜひお気軽にご参加ください。
みなさまとお会いできることを楽しみにしております。